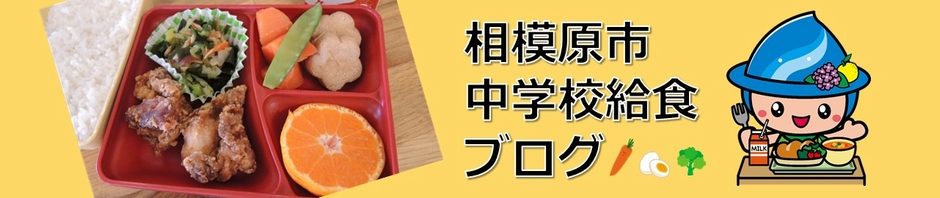【10月11日の給食】
てりやき豆腐ハンバーグ、きのこサラダ、ほうれん草とコーンのソテー、木の葉揚げかにあんかけ、りんご 、ごはん、牛乳(873kcal)
今日は「木の葉揚げかにあんかけ」に使われている「カニ」についてお話したいと思います。
カニといえば、タラバガニやズワイガニが有名ですね。しかし、実はこのどちらかは生物学上、カニの仲間ではないのです。さて、どちらでしょうか。正解はタラバガニです。タラバガニはヤドカリ科で、生物学上はヤドカリの仲間なのです。足の本数も、ズワイガニやカニの仲間が5対10本であるのに対して、タラバガニは一見4対8本しかありません。でも実は、タラバガニの残り2本の足は、甲羅(こうら)の中に隠されているんですよ。機会があればぜひ見てみてくださいね。