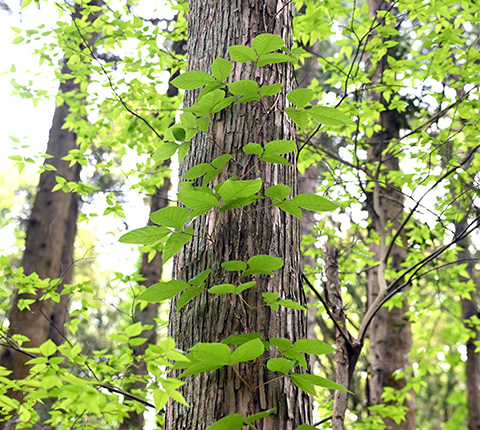5月1日、市内緑区の小山中学校でタンポポの授業を行いました。これは、法務省矯正局が、同校と小山小学校が旧神奈川医療少年院跡地に隣接することから、少年院の敷地内にあった在来種のカントウタンポポを、再整備が終了するまで両校などへ避難させる事業の一環として行ったものです。

カントウタンポポ(写真は博物館お隣の樹林地の株)
小山中の環境委員会の生徒さん向けに、カントウタンポポと、現在路傍などに広く分布する雑種タンポポの見分け方を解説しました。

生育環境の違いなどを説明
雑種タンポポについては先月、このブログでも紹介しました。今年度の環境委員が発足して間もないため、今年初めてタンポポに関わる生徒さんもいます。そもそもタンポポってどんな植物なの?というところから始まり、雑種のできるしくみと、見分け方、そして、なぜこのような活動を進めているのかについて、生物多様性の観点から解説しました。その後、カントウタンポポを栽培している花壇で、花粉を採集します。

中庭の花壇で花粉を採集
花壇のように人の手が大きく加わっている場所では、雑種タンポポが入っいる可能性が高く、実際、この日に咲いていた花の特徴は雑種のものでした。
採集した花粉を室内へ持ち帰り、早速顕微鏡観察します。

中学生なので顕微鏡の扱い方は慣れたものでした
その結果、採集したすべての花の花粉の大きさが不揃いで、雑種と判断されました。

雑種タンポポの花(写真は博物館駐車場の株)
すでに咲き終わっている株も多く、花壇のタンポポがすべて雑種かどうかわかりません。カントウタンポポはすでに花期が終わっている可能性があるため、来年の早春にまた同じ確認作業を行うようアドバイスしました。生物多様性の保全のための活動は、常に科学的に検証しつつ進める必要があります。もし、花壇のタンポポがすべて雑種に置き換わっていたら、少年院跡地から補充する必要がありますし、どのような対策が必要か検討しなくてはいけません。今後、そうしたプロセスについても生徒さんたちと考えていきたいと思います。
(生物担当学芸員)