4月19日、平塚市の相模川河川敷内にある「馬入水辺の楽校」で自然観察入門講座が実施され、当館生物担当学芸員が講師としてお手伝いしてきました。
水辺の楽校とは、市民団体や河川管理者、教育関係者などが一体となって、地域の身近な水辺における環境学習や自然体験活動を推進するため、国土交通省、文部科学省、環境省の3省が連携して進めているプロジェクトです。
今回は、自然観察をとおして水辺の楽校の仲間を増やすため、様々な自然観察の実践を紹介するシリーズの講座の初回でした。朝、集合して早速、たくさん飛んでいるクマバチの観察です。捕虫網で捕まえたい参加者のお子さんのはやる気持ちを少し抑えてもらい、すぐに捕まえずに、飛んでいる様子を観察しました。すると、何のために飛んでいるのか?飛んでいるのはオスか?メスか?などさまざまな疑問が沸きました。そこで、改めて、参加者に捕まえてもらいました。

ケースに入れてクマバチを観察
ケースに入れてじっくり観察すると、顔はかっこよくて、お尻はカワイイ、などの感想が聞かれます。そして、昆虫図鑑を持参していた参加者から、オスとメスの見分け方がレクチャーされました。結果、オスもメスも飛んでいることがわかりました。
この日はいろいろなミッションを用意して取り組んでもらったのですが、その一つが、タンポポの識別です。咲いているタンポポをよく観察して、在来種と雑種、シロバナタンポポなどを見分けたうえで、頭花を採集しました。

タンポポを採集してデータを記入
採集した頭花は、午後の室内実習の際に、花粉を顕微鏡観察しました。
さらに、ルーペを使わないと見つけられない小さな花の観察や植物の分類クイズなど、ふだんはあまり植物を扱わない子どもたちも積極的に参加してくれました。特に、このブログでも紹介したキュウリグサとハナイバナの違いの観察では、キュウリグサばかりの中で、ハナイバナを全員で探し回りました。結果、限られた区域にしか生えていなかったハナイバナを見つけた大人が本気で喜んで盛り上がっていました。
途中、コナラの枝が積んである下の腐葉土に、カブトムシの幼虫がいると子どもたちが教えてくれました。子どもたちは掘って幼虫を見たくてしかたありません。そこで、ここの幼虫をまだ見たことない大人の参加者に対して、子どもたちがレクチャーすることを条件に掘ってもらいました。

おっきい!カブトムシの幼虫
オスとメスの見分け方も大人へ教えてくれています。

子どもの説明に聴き入る大人たち
近くのエノキの大木では、枝が子どもたちの“ゆらゆらイス”になっていました。こんな光景を見ているだけで幸せな気分になります。

エノキの下は休憩所
お昼を挟み、午後は室内で自然観察会をどのような方針で企画するのかという大人向けのお話をしましたが、途中、室内でもできる自然観察のプログラムを入れて、子どもたちにも参加してもらいました。最後には飛ぶタネのモデルとして、ティッシュペーパーだけを使った落下傘作りをして終了。

のりもテープも使わず、ディッシュペーパーだけで作った落下傘
朝から午後までの長丁場の講座でしたが、自然観察は、まずはじっくり見て、それをみんなで共有することが基本であることが伝わったのではないかと思います。
(生物担当学芸員)























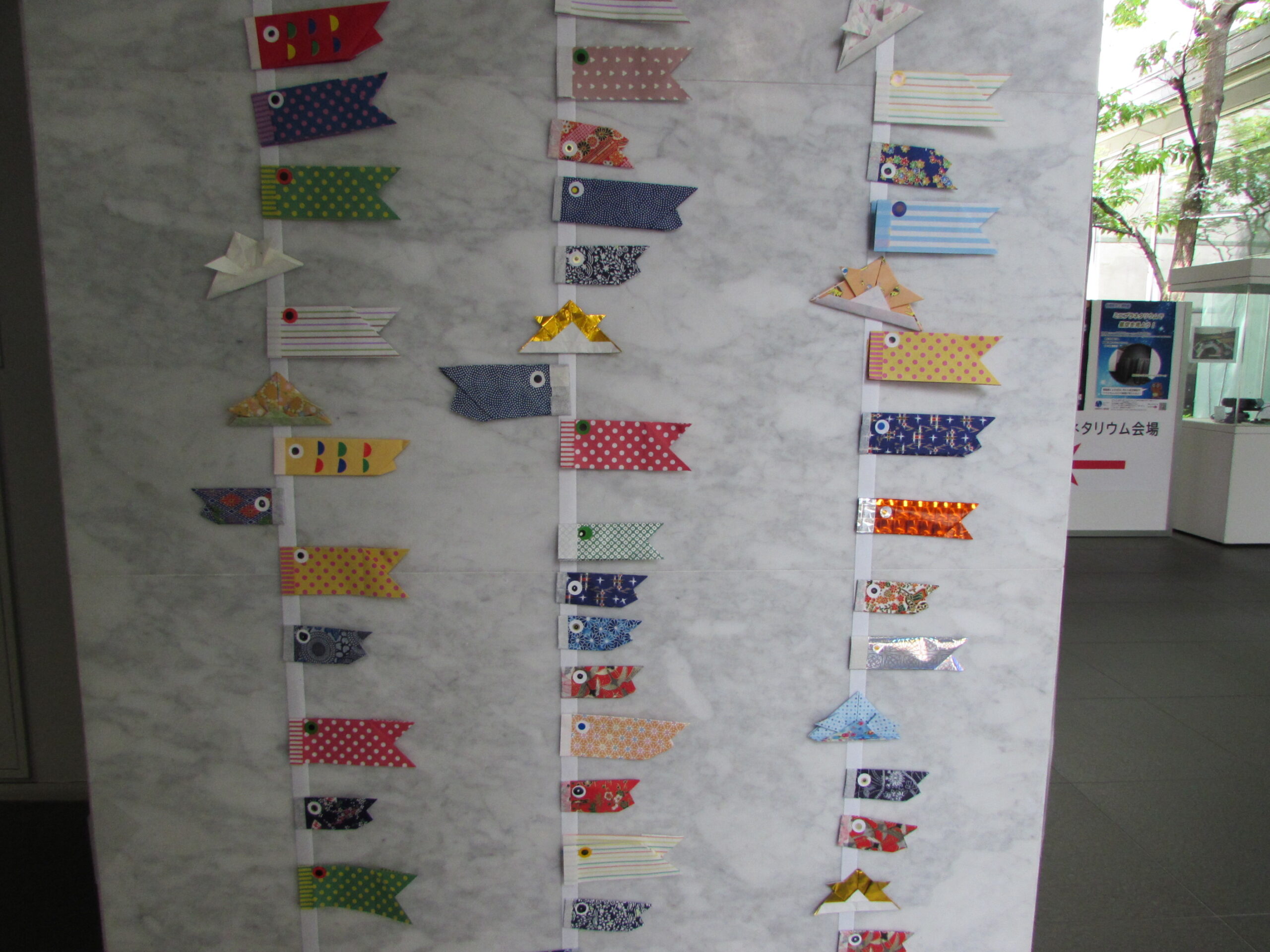




 まん丸の体に、黄色と緑の模様が美しいです。
まん丸の体に、黄色と緑の模様が美しいです。




















