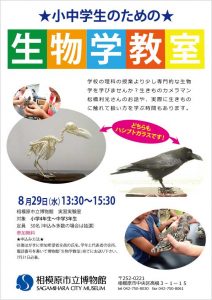博物館の駐車場に消防車!?

火事!?
いえいえ、これは、先日実施した防災訓練の様子です。
二階の喫茶コーナーから出火した設定で、119番通報訓練を皮切りに、来館者役の人に逃げまどってもらい、スタッフが声かけして誘導する避難訓練、初期消火訓練、重要な資料の持ち出しや救護班の活動など、ひととおりの訓練を実施しました。

その後は、AED研修です。
初めて受講する人もいれば、久しぶりの人もいましたが、それぞれ手順を確認することができました。
使わずに済めばそれに越したことはありませんが、いざという時の備えはこれでは整いました。
さて、「いざ」と言えば、実は、この訓練終了時に「いざという時」が発生したのです。
といっても、博物館内で発生したのではなく、どこか管内からの呼び出しがあったようで、署員のみなさんはAED練習用人形の片付けもそこそこに、スクランブル出動ということに。

その臨場感に私たち職員も気持ちが引き締まりました。(その後すぐに回収のために再来館していただけました。)
今回の防災訓練は定例的に行っているものですが、たくさんのお客さまにご来館いただく夏休みシーズンを前に、スタッフ一同が防災の備えをすることができました。
みなさんのご来館を、万全の体制でお待ちしています!
リンク
プロフィール

神奈川県相模原市中央区にある市立博物館です。1995年に開館して以来、相模原の歴史や自然を扱う総合博物館として市民に親しまれ、2019年には入館者数が300万人を超えました。また、2010年7月には、小惑星探査機「はやぶさ」の、2021年3月には後継機「はやぶさ2」の再突入カプセルの世界初公開を行うなど、お向かいにあるJAXA相模原キャンパスとの連携も深めています。
-
最新記事
アーカイブ
カテゴリー
QRコード
タグ
クモ (78) 地質 (73) 歴史 (58) 講座 (52) プラネタリウム (49) 市民学芸員 (47) JAXA (46) はやぶさ2 (41) 観察会 (41) 昆虫 (41) ミニ展示 (39) 野外調査 (37) フデリンドウ (33) 星空情報 (32) 実習生 (30) 尾崎咢堂 (29) 講演会 (28) 尾崎行雄 (28) 吉野宿ふじや (26) ふるさといろはかるた (26) 学びの収穫祭 (25) 紅葉 (23) 民俗 (23) エナガ (22) ジョロウグモ (20) ワークショップ (20) キアシドクガ (18) 尾崎咢堂記念館 (17) カワラノギク (17) はやぶさ (17) 絶滅危惧種 (16) 考古 (16) ミズキ (16) 大河ドラマ (16) 脱皮 (15) 開館30周年 (15) 外来種 (15) 石 (14) クワコ (13) 学習資料展 (13) メジロ (12) 展示解説 (12) カザグルマ (12) カントウタンポポ (12) 自然観察会 (12) 冬芽 (11) キビタキ (11) 臨時休館 (11) がろあむし (11) コブシ (11) どうする家康 (10) 徳川家康 (10) 麻布大学いのちの博物館 (10) ヌルデ (10) 相模原ふるさといろはかるた (10) 舘野鴻 (10) ゲンジボタル (10) クリスマスリース (10) 冬鳥 (10) 出張授業 (10) 雨 (10) 実習 (10) カラスウリ (9) 博物館ボランティア (9) 歴史講座 (9) 議会政治の父 (9) クサギ (9) シジュウカラ (9) バックヤードツアー (9) 眠 (9) 特定外来生物 (9) 探鳥会 (9) 相模川 (9) 羽化 (9) クイズラリー (9) ヒレンジャク (9) チョウ目 (8) 甲州道中 (8) 市民学芸員かわら版 (8) 憲政の神様 (8) 和田義盛 (8) 蔟 (8) エビネ (8) 生物多様性 (8) セミ (8) 幼体 (8) ボランティア (8) スタンプラリー (8) 繭 (8) アブラゼミ (7) カメムシ (7) 雪虫 (7) バードウォッチング (7) ビロードツリアブ (7) ヤマビル (7)メタ情報