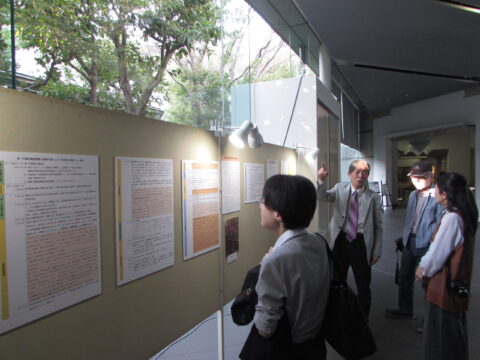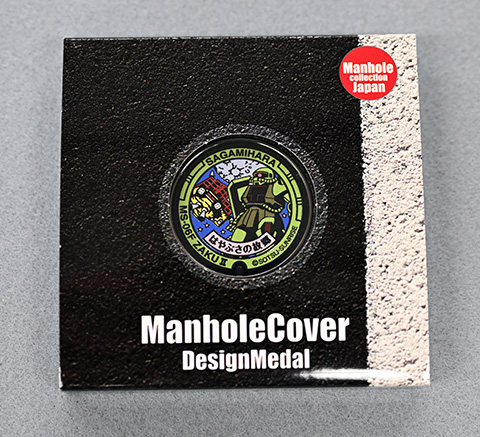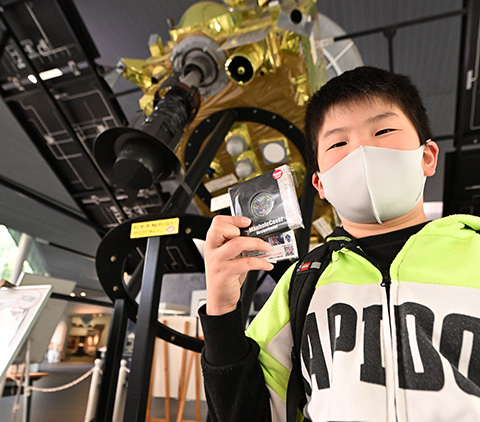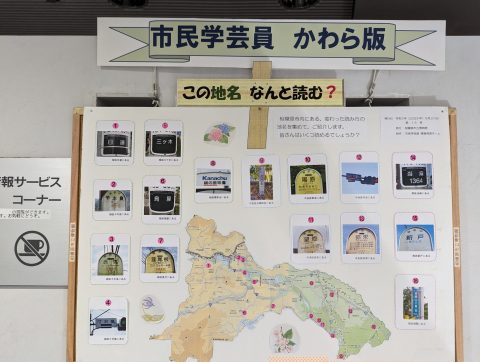相模原市立博物館では、令和5年度学習資料展「子どもの遊び いま・むかし」を開催中です。この企画展は、当館の博物館ボランティア「市民学芸員」との協働によるもので、今回は各世代の子どもたちが夢中になった遊びやおもちゃをテーマに展示しています。
11月5日(日)は、学習資料展の関連イベント「ぶんぶんゴマで遊ぼう!」と「冬の居間のジオラマで写真撮影」を実施しました。そちらの様子を紹介しつつ、展示の見どころを解説したいと思います。

子どもの遊び いま・むかし
まずは関連イベント「ぶんぶんゴマで遊ぼう!」から、ご参加いただいた皆さまの様子を紹介します。このイベントでは、厚紙に好きな色で模様を描いて、凧糸を通し、ぶんぶんゴマを回して遊びます。もちろん、自分で作ったぶんぶんゴマはお持ち帰りOKです。
この日も多くのお子さんがぶんぶんゴマに挑戦してくれました。

自分だけのオリジナルデザイン

遊び方は市民学芸員さんが教えてくれたよ!
続いて、こちらも関連イベントの「冬の居間のジオラマで写真撮影」です。学習資料展では例年、市民学芸員力作のジオラマを展示しており、本年は昭和30~40年代の冬の居間を再現しました。近年では和室やこたつがないご家庭も増えているため、昔にタイムスリップした気分で記念撮影をお楽しみいただけます。

昭和レトロな背景で素敵な2ショット
ここまではイベントの様子をお伝えしましたが、ここからは常設の体験コーナーを2つ紹介します。
まず1つ目は「黒電話にさわってみよう」のコーナーです。今や現役で動いていることがほとんどないといっても過言ではない黒電話ですが、こちらで実際に触ることが可能です。見たことがない世代には目新しく、以前使っていた世代の目には大変懐かしく映るようで、本企画展の中でも好評いただいているコーナーの1つです。
黒電話の横には、市民学芸員が制作した使い方の映像が流れているので、初めての方も安心して体験いただけます。

ダイヤルを回してもしも~し
最後に「トントン相撲」のコーナーを紹介します。
お隣の折り紙コーナーで作った紙人形を土俵に乗せて、「はっけよ~い、のこった!」の合図とともにトントン相撲で競います。トントンと土俵を叩く軽快な音や、「勝った!」、「負けた…」と一喜一憂する声が聞こえるとても賑やかな一画です。

上手に折れたよ!

勝負あり!ママの勝ち~
令和5年度学習資料展「子どもの遊び いま・むかし」は、今月末の11月30日(木)まで開催しています。関連イベントは、あと11月19日(日)の1回を残すのみとなりました。
この日は館内で「学びの収穫祭」のワークショップや、田子学芸員(天文担当学芸員・気象予報士)による講演会「どうして空は青いのか?~身近な気象と観天望気~」を開催します。ぜひ当館へおでかけください!
(歴史担当学芸員)
※写真は全てご了承のもとブログに掲載しています。




.jpg)