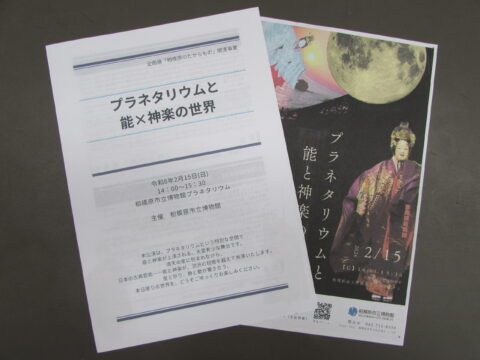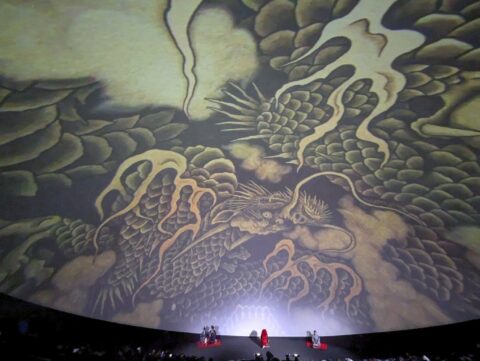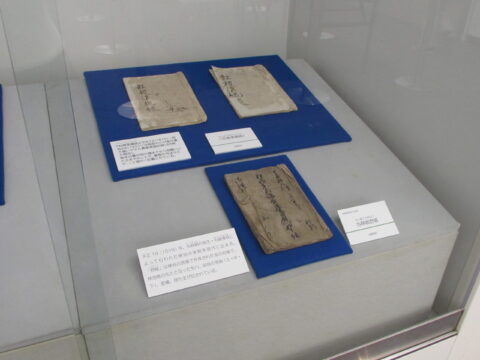2月15日、厚木市のアミューあつぎで今年度の丹沢大山自然再生報告会が行われました。これは、丹沢大山自然再生委員会が毎年開催しているシンポジウム形式の報告会です。この委員会には当館の生物担当学芸員が事業評価・調査部会長として参画しており、このシンポジウムでもパネルディスカッションのモデレーターを担いました。

パネルディスカッションの様子
丹沢大山自然再生とは、1980年代から顕著になった丹沢山域の生態系の異変に対し、市民団体、企業、マスコミ、専門家、行政機関など多様な主体が結束して調査研究や普及を行う活動です。ここ数年は、高標高域のブナ林の衰退やシカの食害による林床植生の衰退といった主要なテーマに加えて、里地里山域の保全が大きなテーマとなっています。それは、生物多様性条約の中で提唱されているネイチャー・ポジティブの実現には、私たちの生活域やその周辺の生物多様性を高めることが不可欠だからです。

麻布大学の村山教授も、iNaturalistを用いた生物情報の蓄積について紹介
パネルディスカッションでは、AIなどデジタル技術を用いた生物多様性情報の蓄積や、企業によるネイチャーポジティブの取り組みなどが紹介されました。

主会場は満席でした
今年は神奈川県自然保護協会主催による「さがみ自然フォーラム」との共催となり、満席の会場に加えて、オンラインで結ばれた全国の参加者のみなさんと活発な議論が行われました。
(生物担当学芸員)

-scaled.jpg)