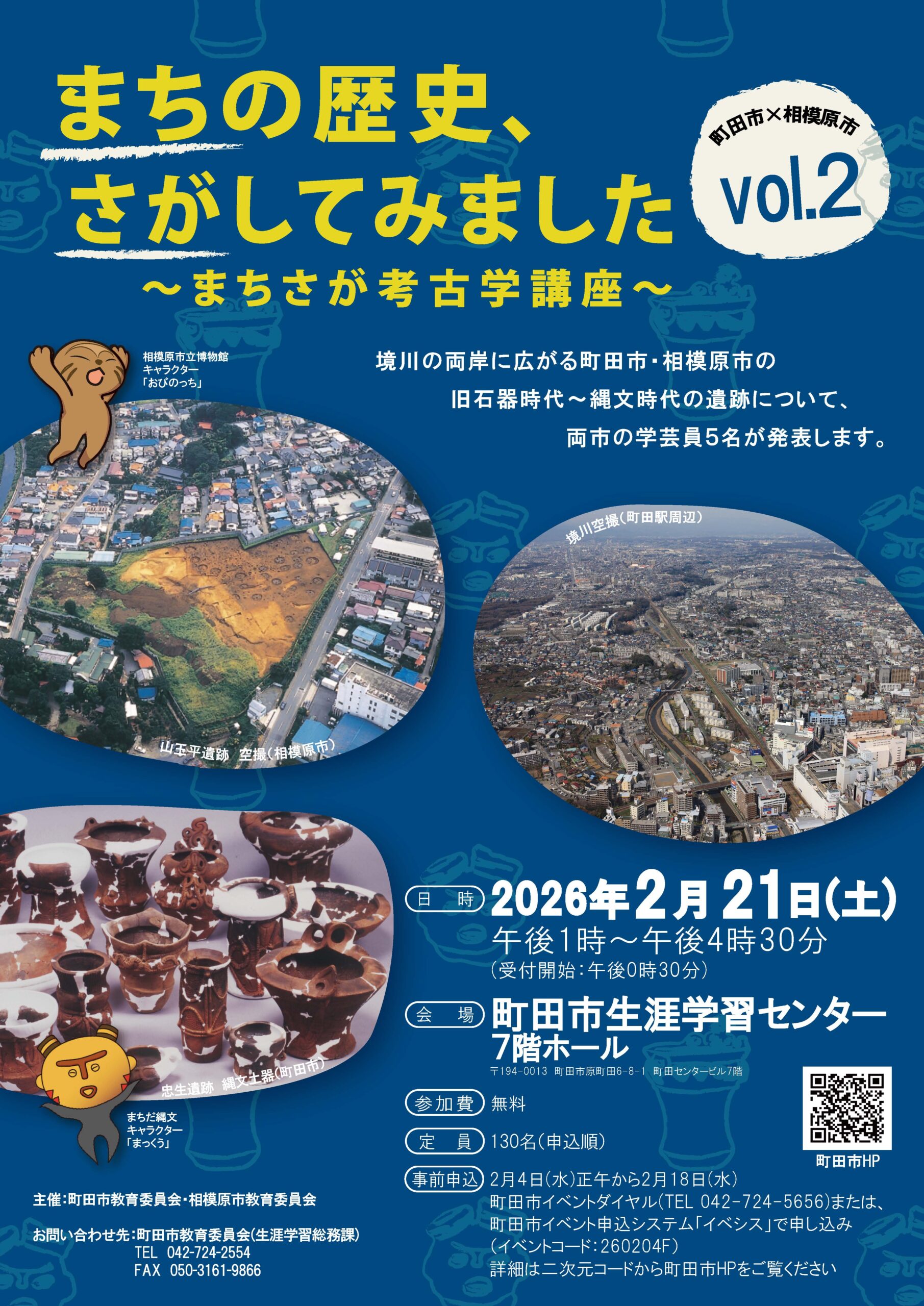相模原市立博物館で現在開催中の企画展「相模原のたからもの」の関連事業として、講演会「レジェンド学芸員が語る相模原の宝」を1月31日(土)に開催しました。 今回は通常の講演会とは趣向を変えて、若手学芸員の質問に答える形式で当館の元学芸員3名にお話しいただきました。ご登壇いただいたのは、歴史が専門の大貫英明さん、生物が専門の守屋博文さん、そして、民俗が専門の加藤隆志さんです。いずれも、相模原市の文化・歴史・自然を知り尽くしたレジェンドの3名です。
今回は通常の講演会とは趣向を変えて、若手学芸員の質問に答える形式で当館の元学芸員3名にお話しいただきました。ご登壇いただいたのは、歴史が専門の大貫英明さん、生物が専門の守屋博文さん、そして、民俗が専門の加藤隆志さんです。いずれも、相模原市の文化・歴史・自然を知り尽くしたレジェンドの3名です。
まず、自己紹介がわりに、「レジェンド学芸員が選ぶこの一品」と題して、思い入れのある博物館資料を紹介していただきました。

大貫英明さんが選んだのは「田名坂上遺跡出土の三彩小壺」

守屋博文さんが選んだのは「クロサワツブミズムシ」

加藤隆志さんが選んだのは「柳田國男の葉書」
最初の説明で、一気に聴衆を惹きつけました。さすがレジェンド学芸員!見事な語り口です!
途中からは現役若手学芸員を代表して、歴史担当の眞壁学芸員がレジェンドに質問をしました。
博物館の開館前の準備室段階や開館後の苦労話も交えながら、和やかな雰囲気で進行しました。
和やかな雰囲気ながらも、文化財や博物館資料を未来へ守り繋げていくために必要なことを熱く語っていただきました。会場からも質問があり、大盛況のうちに講演会を終えることができました。
当日は多くの方にご聴講いただきました。この講演会が地域の文化財や博物館資料について、また、それらを後世に残していくためには何が大切かを考えるきっかけになれば幸いです。
ご登壇いただきました大貫さん、守屋さん、加藤さん、ご聴講いただいた皆様、ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
(地質担当学芸員)