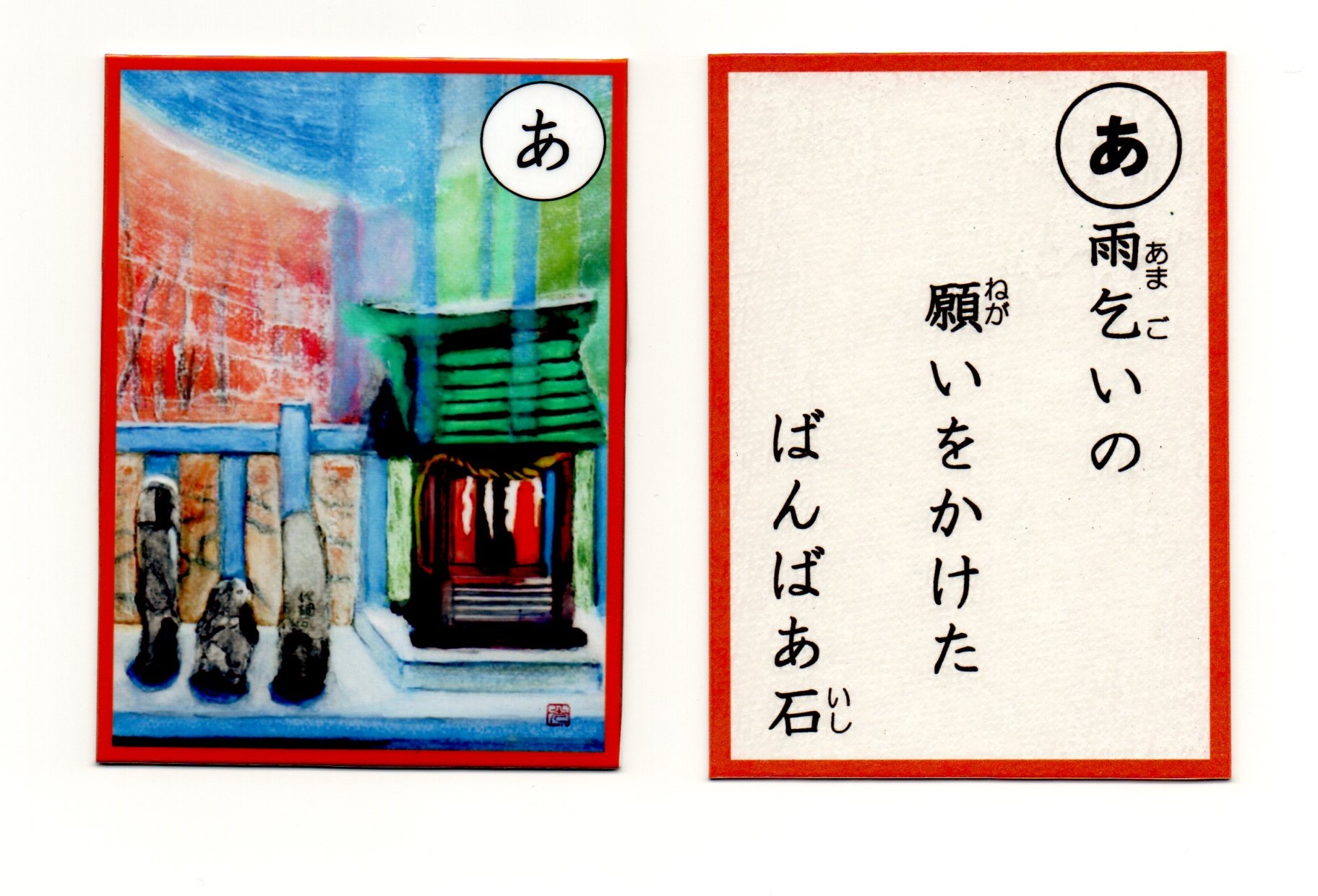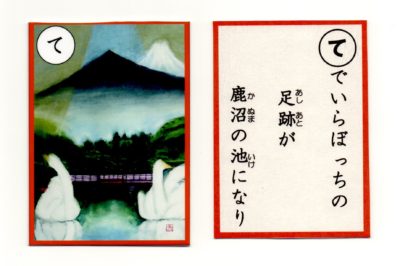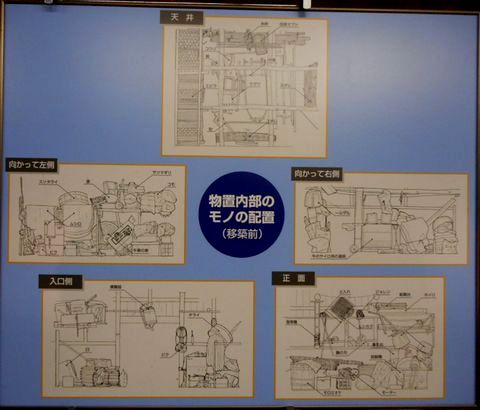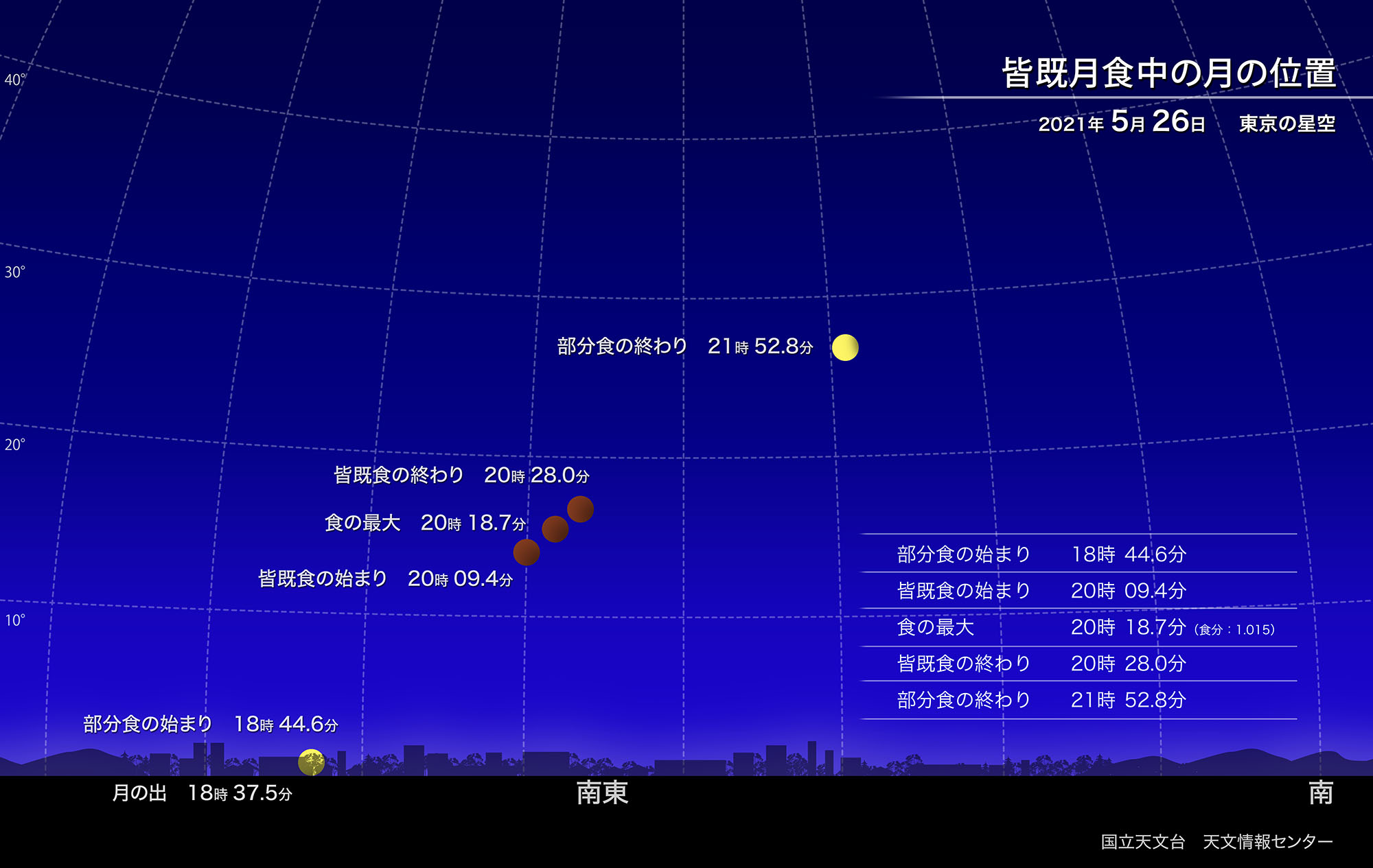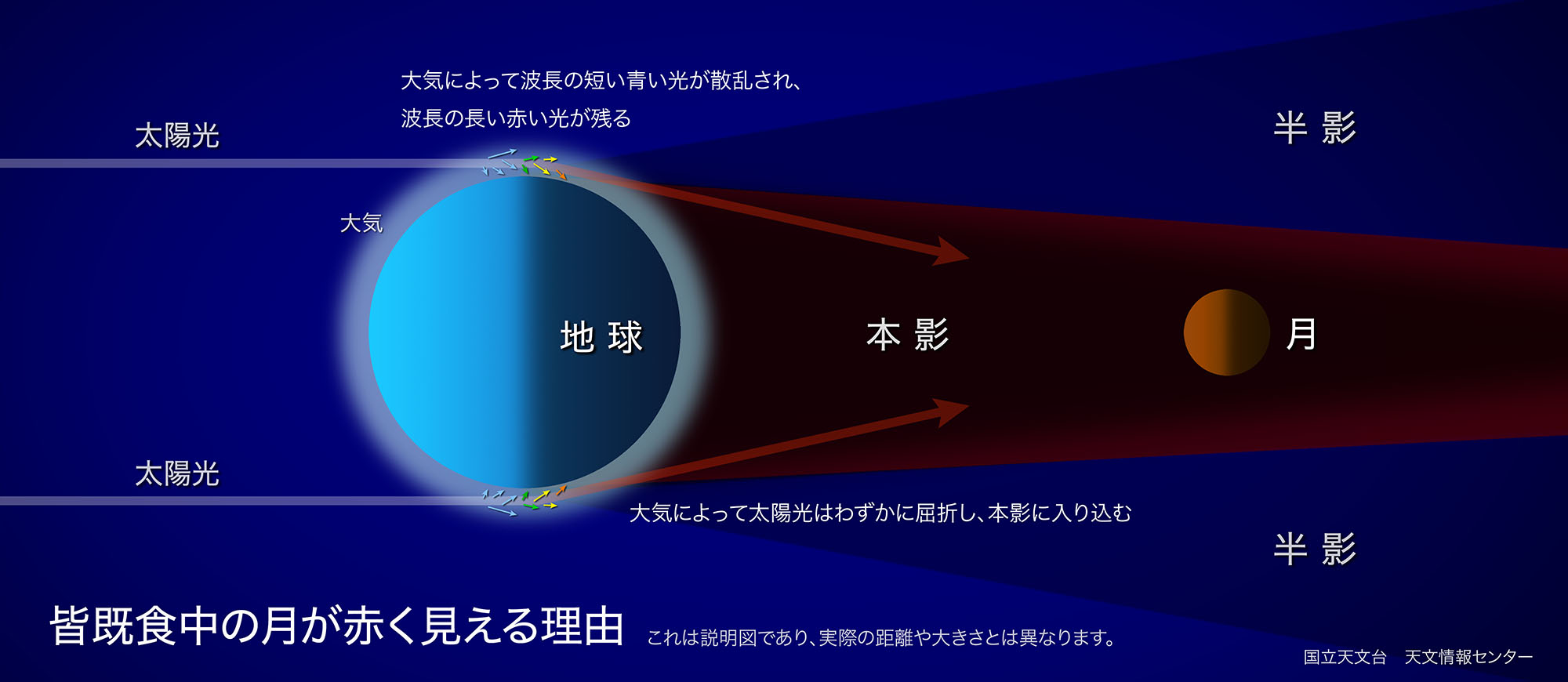5月28日、市内の県立上溝南高校のホタル観察会のお手伝いに行ってきました。前日の大雨から一転、穏やかな初夏のお天気となったこの日、日没後には西の空に夕焼けが広がりました。
あたりがだいぶ暗くなってきた頃、50名近い高校生たちが中央区のゲンジボタル生息地へ到着(ストロボが邪魔になるため、全体の写真は撮影していません)。生息地の環境や、この場所のゲンジボタルが100パーセント天然のものであることなどを説明した後、それぞれにカウンターを持ってもらい出発です。点滅するゲンジボタルの数を数えながら歩きます。サクラの満開から2か月後あたりがゲンジボタルのピークになります。ちょうど今年は今ごろがその季節。歩き始めてすぐにゲンジボタルを見つけられました
場所によってゲンジボタルの多いところと少ないところがあり、そんな環境の様子も見ながら歩いてもらいました。
ゲンジボタルだけではなく、カエルも豊富なこの場所。カエルの大合唱の音量の大きさにみなさん驚いた様子。こんなふうに、アマガエルが鳴のう(のど袋)を膨らませて鳴いているのを初めて見た!と感激している生徒もいました。
それぞれのカウント結果は、後でしっかり集計していただくことにしていますが、だいたい往路で60~70、復路で80~100くらいを数えました。風もあったせいか少し少なめでした。ピークはまだもう少し先になるかもしれません。
この日の体験から、高校生たちがゲンジボタルをとおして身近な環境について考えるきっかけになればよいなと思いました。