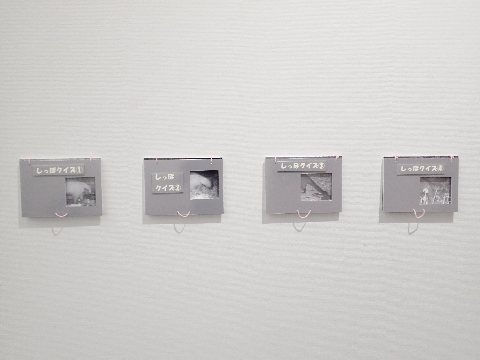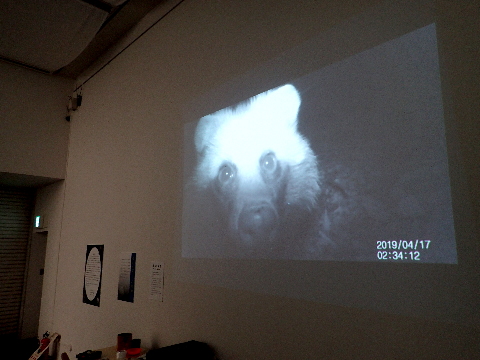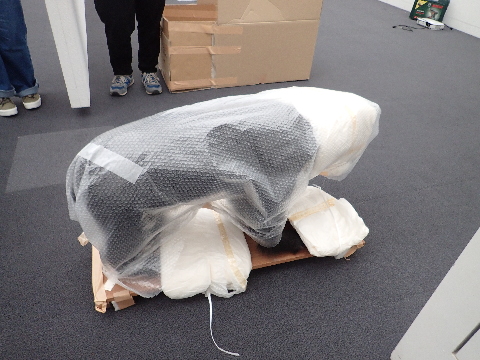5月25日、毎月恒例の生きものミニサロンを実施しました。今回のテーマは「ムシムシ天国!いろいろな虫を観察しよう」です。
小学校の運動会が多い日なので参加者がいるかな?との心配をするまでもなく、20名以上の方と楽しくたくさんの虫を観察できました。まずは、下見の時に見つけたこちらを館内で観察してから出発。

美しいカメムシです!
アカスジキンカメムシです。赤と緑のピカピカに、歓声が上がりました。
そして、外へ出ると早速こんな虫がお出迎え。マイマイガの幼虫(毛虫)です。

マイマイガの幼虫
小さいうちは毒の毛を持ちますが、大きくなると毒が無くなることを説明すると、中には手にとってじっくりと観察される参加者もいました。クレイアニメの主人公のような顔つきですね。
そして、数日前に館内で捕獲されたヤモリを館外へ逃がすセレモニー?を。

かわいい手や顔つきが大人気でした
撮影会のようですね。

逃がしたヤモリをモデルに撮影会
そして、クワの木に移動して葉裏に群れる白いモジャモジャを観察しました。

よく見ると動いています
これはクワキジラミの幼虫なのですが、足があってモゾモゾ動いてる!と大きな声が上がりました。そもそも虫であることにみなさん驚かれたようです。
そして最後に、草についているこんな泡を観察しました。

草についている泡の正体は?
これは卵?いえいえ、泡を取り除いてみると・・

アワフキムシの仲間の幼虫
こんな虫が出てきました。アワフキムシの仲間の幼虫です。お尻がテールランプのように赤いのが特徴です。
クワキジラミはろう物質でモジャモジャを、アワフキムシは液体を出して後ろ足でかきまぜて泡をつくります。どちらも身を守る方法なのでしょう。
身近なところにも、こんな不思議な形の虫がいることがちょっと新鮮だったようです。あっという間の30分でした。
次回は6月22日(土)12時からです。