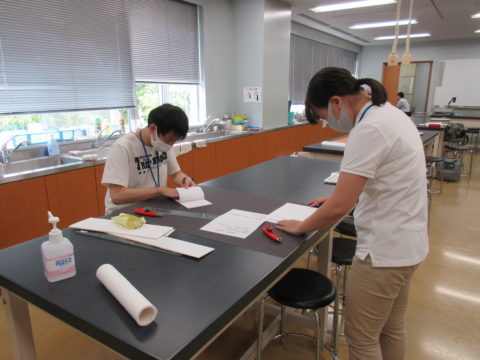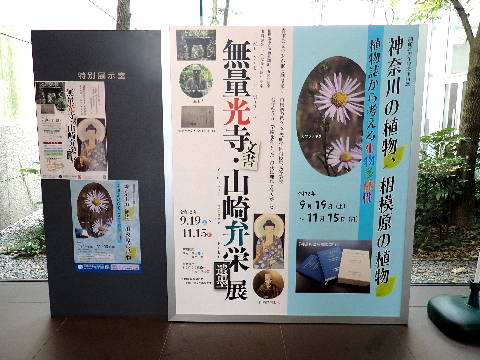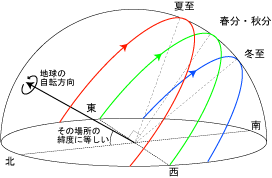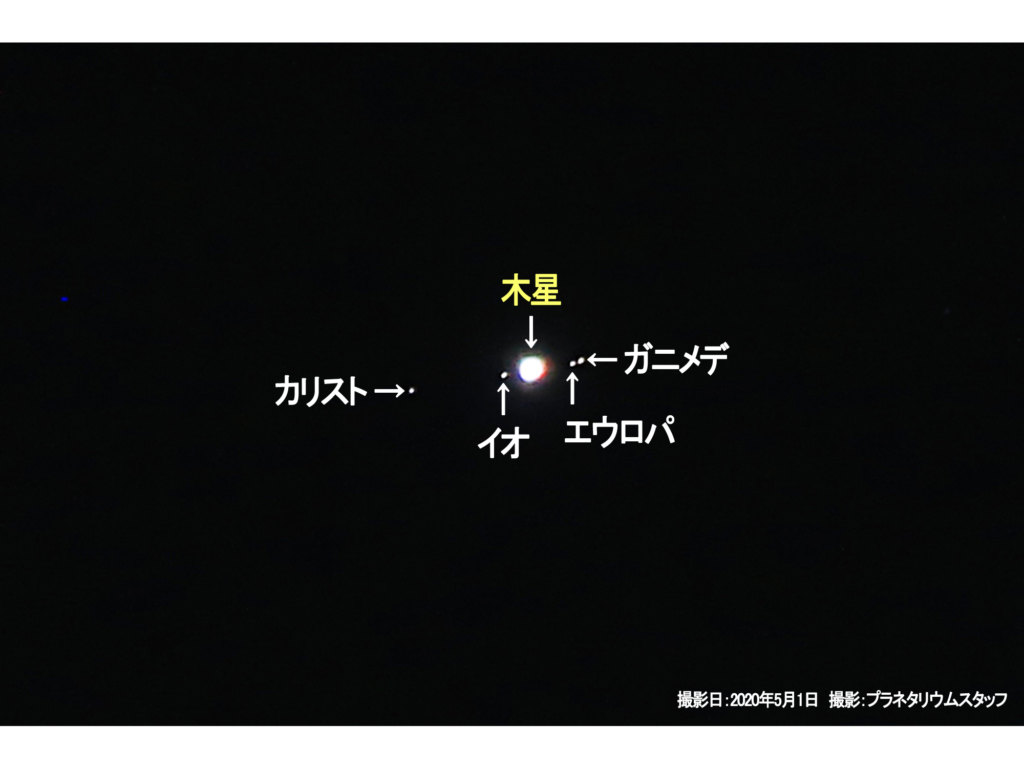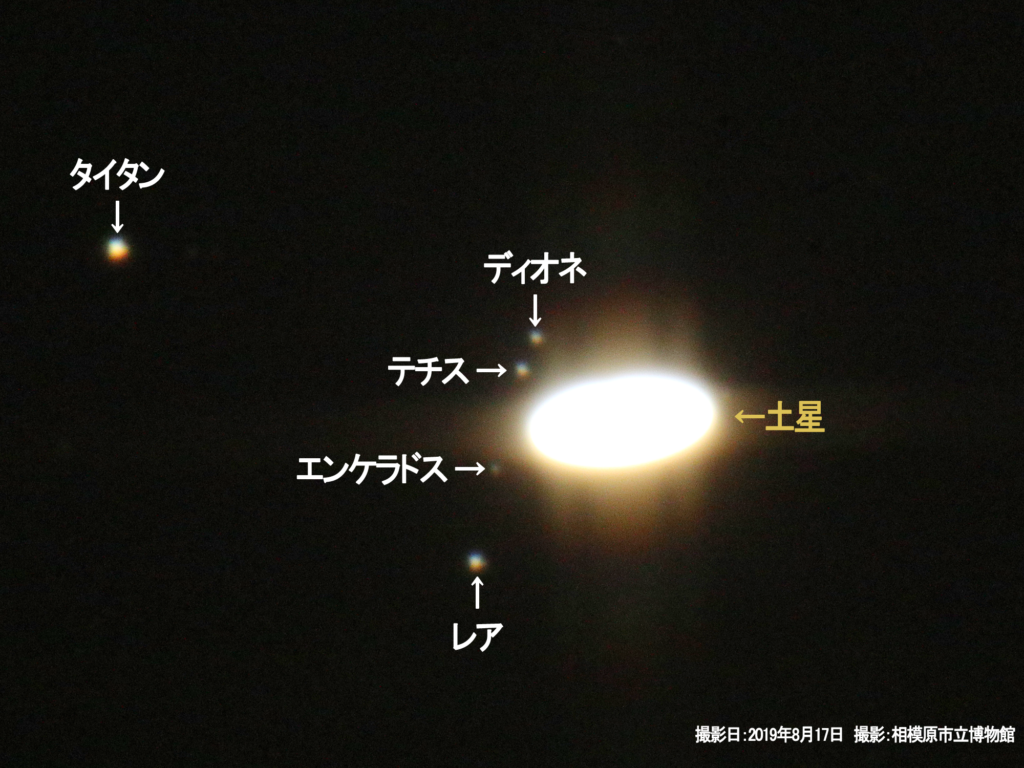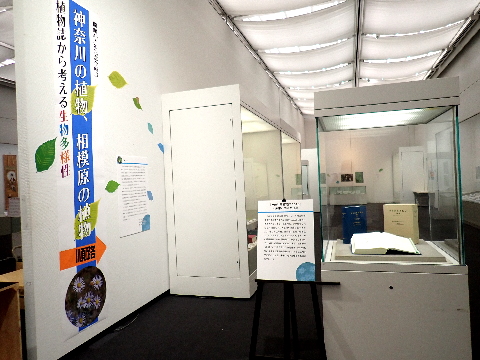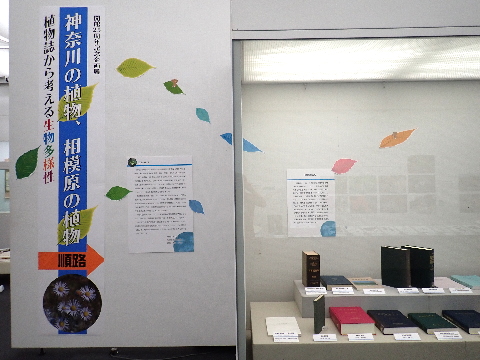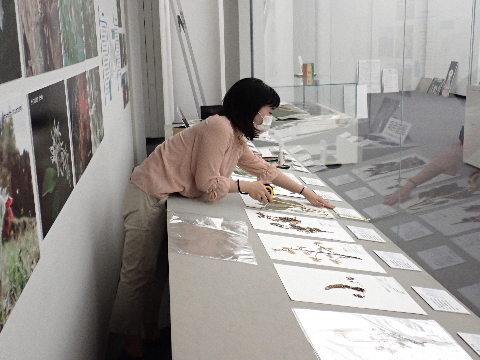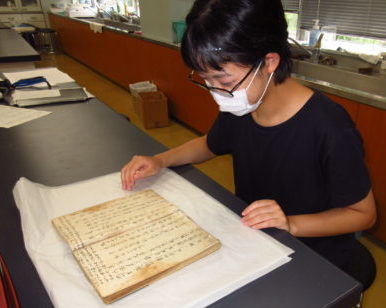江戸時代までの日本は、いわゆる旧暦(太陰太陽暦・たいいんたいようれき)を使っていましたが、明治6年(1873)から新暦(太陽暦)に変更され、現在では年中行事もほとんどが新暦の日程で実施されています。
そんな中で現在でも多く旧暦で行われているのがお月見で、写真は、平成25年(2013)9月21日の見事な十五夜の満月です。

旧暦8月15日の満月の日に行われるのが十五夜、旧暦9月13日が十三夜で、旧暦のため日取りが毎年異なり、ちなみに今年は10月1日が十五夜で、十三夜は10月29日となります。また、「片月見はいけない」とも言われ、十五夜の月見をしたら十三夜も祝うとされていました。
これらの日には、月を臨める縁側などに机を出し、その上にススキやカヤ、オミナエシなどの秋の花を花瓶に飾ります。また、団子やサツマイモ・里芋などの秋の収穫物をお供えし、このほかにも月にちなんでマンジュウなどの丸いもののほか、豆腐を供えることもあります。
今回紹介するのは、すべて南区下溝の古山集落での撮影です。最初の写真は昭和63年(1988)10月23日の十三夜で、縁側にススキを飾り、左側には芋類が供えられています。

この日には各家でそれぞれ供え物をしますが、一軒ずつ回ってみると供えられているものが違っているのが分かります。以下の写真は、平成22年(2010)9月22日の十五夜の際で、最初の写真では丸いリンゴとマンジュウのほかに豆腐が置かれており、次は、芋類のほかに鮮やかなオミナエシの花が飾られているのが目に付きます。


さらに芋類やマンジュウ・豆腐のほかに、団子や落花生が供えられている家もありました。


ところで、これまで紹介した写真の多くにお菓子があるのに気が付かれたでしょうか。十五夜・十三夜の夜には、地区の幼稚園児や小学生などが場合によっては保護者とともに「お月見ちょうだいな」などと言いながら各家を回り、供えられているものを貰うことが行われています。かつては芋などの月への供えものを貰いましたが、こういうものでは子どもたちが喜ばないということで、お菓子を配ることに変わりました。
写真は、昭和63年(1988)10月23日と平成22年(2010)9月22日の子どもたちが各家を訪れている様子です。まるで本来のハロウィンのようですね。


お月見の供え物を子どもが各家を回って貰って歩くことは、古山集落のほかにも市内各地で見られ、現在でも子ども会の行事などとして行われている地区もあります。古くは子どもに配るのではなく、子どもたちが誰にも知られないようにそっと持っていくとされ、また、子どもに与えるとよいことがあるとも言われました。
最後に、十五夜に供えたカヤやススキは、泥棒よけになるなどと言って翌日の朝に家の入口や屋根に放り上げることがありました。写真は昭和63年(1988)2月・緑区相原の撮影で、戸袋の上に置かれています。
以前に紹介したお盆の造花を外便所に置くことと同様に、行事に使われたものはそのまま捨てられることもなく、別のさまざまな役割を期待されることもありました。