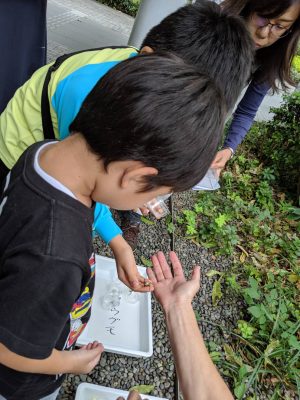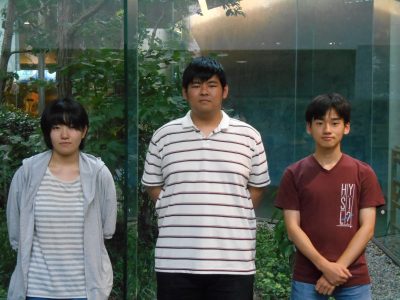こんにちは、民俗分野実習生の九嶋です。
今回、私は展示の作成で印象に残ったことについてふり返っていきたいと思います。
私たち民俗分野の実習生は「講中(こうじゅう)」をテーマに展示を作成しました。
講とは、本来、ある目的のために集まる集団のことで、宗教的、経済的、社会的な面で協力していました。

展示ケースに初めて入りました!
具体的な作業の内容は、展示のねらいを考える、展示する資料を選ぶ、資料について調査しそれを基に展示の解説パネルを作る、展示に必要な器具を準備する、資料や解説パネルをケースに列品する、などがありました。
その中で私の印象に残ったのは、展示に必要な器具を準備する時のことです。
今回、民俗分野では、葬式の時に土葬の穴掘り役が着用していた半纏(はんてん)を展示することになっていました。その半纏の袖に棒を通して上から吊す形で展示しようと考えていましたが、丁度良い長さの棒が無かったので、突っ張り棒に梱包材や紙を巻き付けて展示に使用する棒を作りました。
このように、既製品の器具を使うだけではなく、必要に応じてその場で作るということがとても柔軟な対応を求められると実感でき、勉強になりました。

列品が終わり最終確認中
ここからは、野月が展示解説での印象等をふり返っていきたいと思います。
9月15日は実習最終日ということで、これまで学んできたことの総まとめとして実習生展の展示解説を行いました。
初めは実際に人前で解説するということもあり、うまく説明できるか、理解していただけるか不安でいっぱいでしたが、来ていただいた皆さんとコミュニケーションを取り、会話を楽しみながら解説することができました。
私たちの目的は「どうやって『講中』に興味を持っていただくか」ということでしたが、私たちの説明を聞いて共感してくださったり、自分の経験を話される方も多く、こちらも沢山の勉強となった実りの多い展示解説となりました。

展示解説の様子
最後に足立がまとめをさせていただきます。
9月15日で実習期間は最終日を迎えました。9日間、どの実習日をふり返っても新しい学びとの出会いでした。博物館が現在どんな役割を果たしているのかを知れたことが私は一番勉強になりました。
他にも実際に現場を経験しなければ分からなかった発見がたくさんあり、実習から得たことは決して忘れず、これからの取り組みに活かしていきたいです。
学芸員さんをはじめ、実習に関わってくださった市民学芸員と市民ボランティアの方々から、多くのご指導をいただき、貴重な勉強をさせていただきました。本当にありがとうございました。
実習生の展示は10月20日(日)まで特別展示室にて開催しています。実習生が苦労の末に展示を完成させたので是非見に来てください!
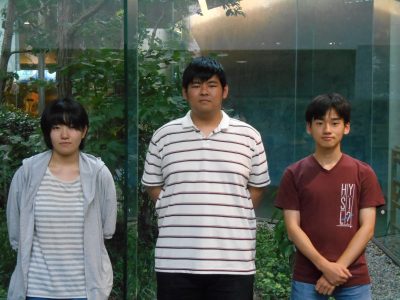
民俗分野実習生3名