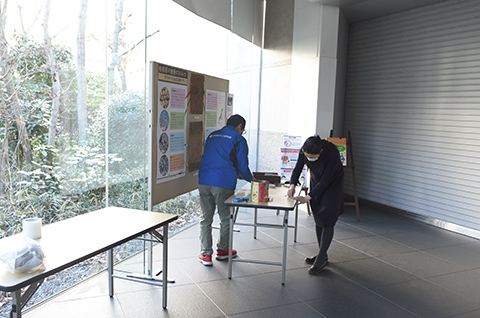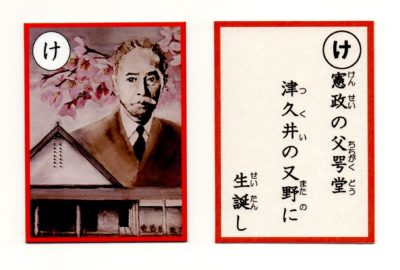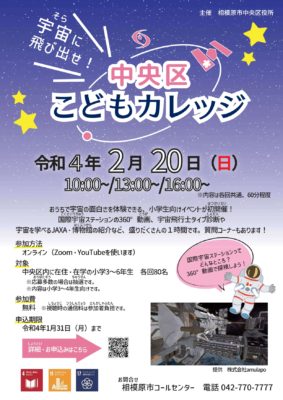1月21日、翌日の「生きものミニサロン」の準備のために博物館前庭を歩いていたら、博物館の敷地内で今年最初の花を見つけました!
ウグイスカグラです。毎年、真冬のこの時期から咲き始めるトップバッターで、春まで順番に少しずつ咲き続ける息の長い花です。ちょうど、ご近所の大野村いつきの保育園のみなさんがいつものようにお散歩に来ていたので、一緒に観察しました。
花の香をかいでいた園児が「いいにおいがする!」と言うので、自分でもかいでみました。残念ながらにおいはわかりません。「ほんとだ!甘い!」とか「鼻がつまっていてにおいわからない」とそれぞれ自分の感想を言ってくれていたので、気分でにおいを感じたわけではなく、本当に香ったのだと思います。普段からこうした感覚が研ぎ澄まされているのでしょう。このままでは悔しいので、もう少し花が咲き揃ってきたらもう一度チャレンジしてみようと思います。
そして、そんな観察をしていたら、足元灯の内側をのぞき込んでいた子が、「なんかいるよ」と教えてくれました。
確かに、何かの虫の繭殻(羽化した跡)がありました。残念ながら何の虫の繭かはわかりませんが、虫がこんなところを利用していることにちょっと驚きました。
毎日博物館にいても、こんな場所に目を向けることはありませんでした。私たち大人とは違う視点や鋭い感覚を持った園児たちから、今日も生きものの見どころを学びました。