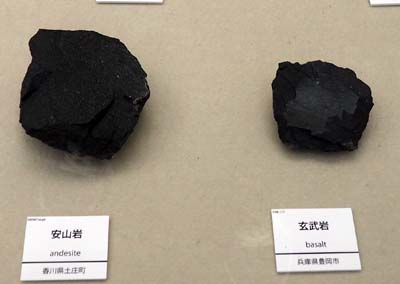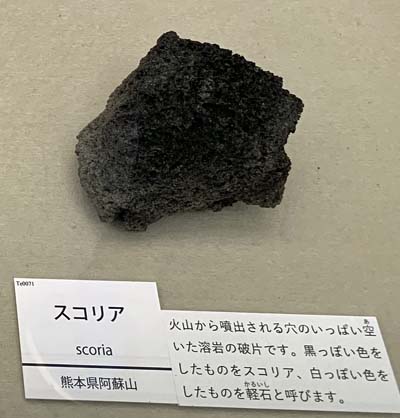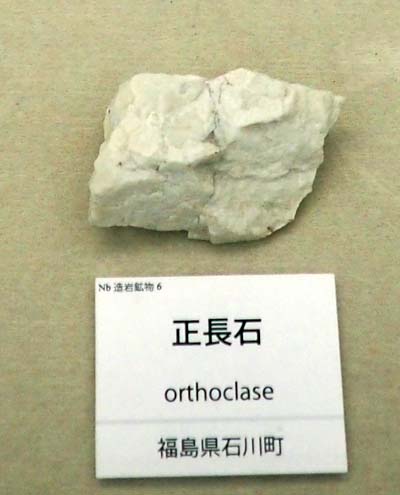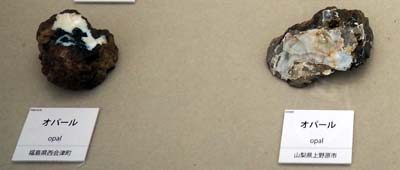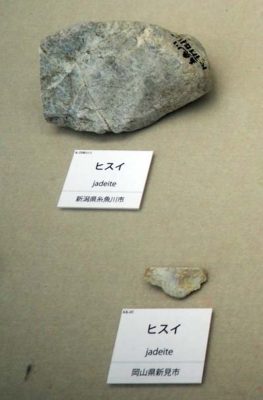的祭の 豊作占う 田名八幡宮
(まとまちの ほうさくうらなう たなはちまんぐう)

中央区田名の鎮守である田名八幡宮では、毎年1月6日に的祭(まとまち)が行われます。
この祭は、境内に設置された大きな的に3歳~5歳の4人の男児が矢を射て、その当たり具合で吉凶を占い、邪気を祓って豊年に導く神事とされています。起源は、源頼朝の時代とも、元禄時代であるともいわれ、わかっていません。相模原市の無形民俗文化財に指定され、初春に実施される行事として見学者が多く集まります。

平成23年1月6日撮影
的祭で使用する的と弓矢は近隣の酒井家が代々作っています。
的つくりのことを的踏みといい、的は葦(あし)で網代(あみしろ)風に編み、中央の黒丸は焼いたナスの茎の灰を混ぜた墨で描きます。葦はかつては緑区葉山島のものを使っていましたが、現在は他所のものを使っています。

平成17年1月4日撮影
網代に編む
弓は5張で、かつては緑区葉山島の桃の木を使いましたが、今はないので榎を使います。矢は酒井家の篠竹で、6本ほど作り、矢羽は半紙で作ります。
6日の午前中は、あらかじめ境内に作られた竹でできた枠組みに鉤(かぎ)を掛け、そこに的を取り付けます。
午後になると神事が開始され、くじ引きで矢を射る順番を決めます。
射手(いて)の男児は3歳~5歳までの長男4人で、前年に不幸のなかった家から選ばれます。
4人は裃(かみしも)を着け、父親の介添えで社殿を3周します。

平成20年1月6日撮影
社殿を3周する
そして、4人が交替で3回ずつ計12本、的に向かって矢を射ります。
一の矢は天下泰平の神の矢、二の矢は領地安全の地頭の矢、三の矢は五穀豊穣の百姓の矢という伝承がありますが、現在では地域や人々の発展を願って射ると読み替えられています。
矢が中央に当たると良いとされ、最後に総代長が今年の世相を占います。

平成24年1月6日撮影
かつては神事が終わると、的・矢・鉤を奪い合って家へ持ち帰り、無病息災、一家繫栄の縁起物としました。特に、鉤を取ると蚕が当たるとされてきましたが、けが人が出たこともあり、現在ではその奪い合いは行われていません。
この的祭のように、弓で大きな的を射ることによって、神意を占う神事は一般に御歩射(おびしゃ)と呼ばれます。
全国的にありますが、特に関東地方で多く行われています。神奈川県では、相模原市以外に川崎市や大磯町に分布していることが知られています。
その中でいくつもの共通点がある一方、的の作り方や弓の素材、矢を射る所作など細部については、各地域の生活様式と深く結びついており、大きな違いが見られます。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を配慮し、的祭は開催見合わせになりました。再開した際には、細かい部分にも注目してみてください。
・このかるたは、当館のボランティア市民学芸員が2017年に制作したものです。
・このかるたは、博物館にて貸出し可能です(現在は当面の間、貸出しを休止しております)。
・貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください。(042-750-8030)
・貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒などを必ず行ってください。