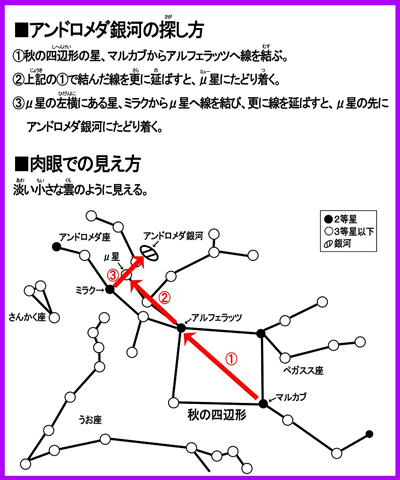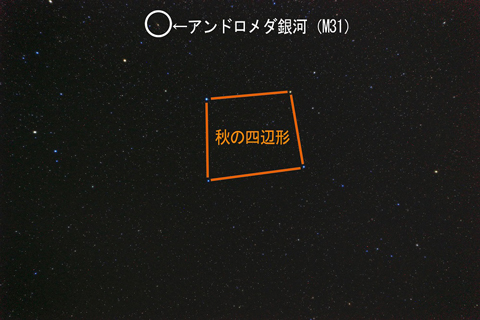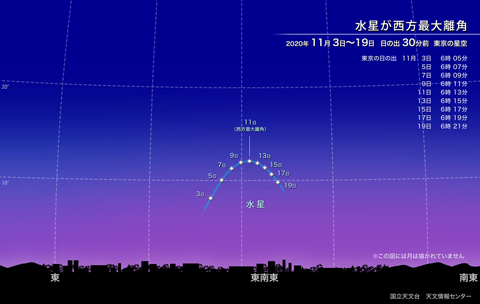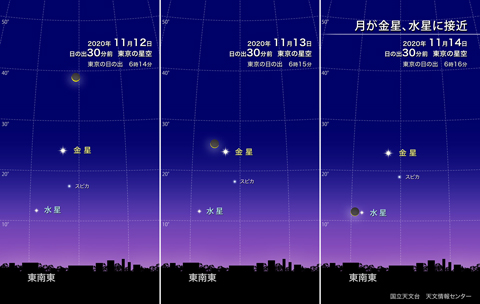サツマイモや陸稲(リクトウ・オカボ)の収穫に忙しいこの頃は、冬作の麦類(大麦・小麦)の種蒔きの時期で、10月下旬から11月上旬にかけて小麦を蒔き、その後に大麦を蒔きました。かつては、次回取り上げる予定の11月20日のエビス講までに蒔き終えるのを目安としていました。
今回も昭和62年(1987)度制作・文化財記録映画第六作「相模原の畑作」において、中央区田名で撮影された麦蒔きを中心とした写真を紹介します。
最初の写真は陸稲を植えていた畑に小麦を蒔くために、畑を耕しているところです。陸稲は畑にまだ麦が残っている時に蒔きますが、麦は陸稲収穫後の畑をうなって(耕すこと)種を蒔きます。
麦の種も陸稲と同様に肥料と混ぜて蒔くのが普通で、別々に蒔くよりも手間が省けるとも言われました。肥料と混ぜた種を、ツミオケと呼ばれる桶に入れて蒔いていきます。それが後には、種を入れて振るように蒔く播種器が出てきて、先に肥料を撒いて後から種を振ることも行われるようになりました。写真では、奥のツミオケで蒔く手前で播種器を振る様子が見えます。
麦は陸稲だけでなく、サツマイモ畑にも蒔きます。サツマイモは芋を鍬で掘り出して収穫するため耕した状態と同じになるため、蒔き溝を付ければ播種できます。写真では、前回の職員ブログで紹介した、サツマイモを保存するために畑に掘った穴の目印に差した藁束が左奥に見えています。
そして、麦を蒔いたところに陸稲と同じく、足で土を蹴るようにして種の上に掛けていくホウリモノの作業を行います(以上、昭和62年(1987)11月8日撮影)。
冬場の寒い時期に畑にある麦は、霜柱などで根が浮き上がらないように何回か麦踏みをする必要があります。映画では昭和63年(1988)1月15日に麦踏みを撮影しましたが、この頃の小麦は写真のような様子で、麦の状況を見ながら踏んでいきます。
また、やはり寒い時期なので、麦株の北側に土を寄せて風をよけ、太陽がよく当たるようにしたり、さらに、刈り取っただけで畑に残ったままの陸稲の根を掻き出す作業などもありました(以上、1月15日撮影)。なお、陸稲を蒔いた後の麦の根上げについては、職員ブログNo.30の「陸稲の収穫」で触れています。
この後もいくつかの作業を経て、これも職員ブログNo.13で紹介したように6月に麦の刈り取りと脱穀調製が行われました。収穫された大麦は米などと混ぜて主に自家の食事の麦飯に、小麦は粉に挽いてウドンや酒マンジュウの材料にするほか、出荷して売ることもありました。
畑が圧倒的に多かった市域にとって、大麦や小麦は日常食はもちろん、行事の際の食物の材料や販売用の現金収入源としても、この地域の生活を支える非常に重要なものの一つだったのです。