【メンテナンス休館のお知らせ】
6月23日~25日は、展示室の清掃及び設備メンテナンスのための休館となります。ご不便をおかけいたします。
この週末に入ってから、博物館のまわりをギャーギャーとけたたましく鳴きながら飛ぶ鳥の群が目立っています。その鳥とは、ムクドリです。

ムクドリの若鳥 暑いせいか、口をあけている個体が多くいました
駐車場の地面で何かをついばんでいたかと思うと、飛び立ってケヤキの樹上で休息したり・・

樹上で羽づくろいするムクドリの群
お隣の樹林地でやたら大騒ぎしていると思ったら、先日のブログでも紹介したヒメコウゾの果実を食べていました。

ヒメコウゾの果実
ただ、この果実がお目当てかと思っていたら、入れ代わり立ち代わり10羽前後の群が出入りしていて落ち着きません。
このムクドリの群は若い個体(今年産まれて巣立った若鳥)を中心に集まっているようで、おそらく、あまり統率がとれていないのだと思います。気になるところへ気の向くままに動き回っている、という印象でした。それにしても動き回るたびにギャーギャーと鳴くので、博物館の守衛さんも何事かと驚いていました。その無節操な飛び回り方を見ていると、鳥の暴走族といった雰囲気でした。

駐車場の地面もこれといっておいしいものがたくさんあるわけでもないのですが・・たまにイモムシなどついばんでいるようでした
若い群は夕方になると、ねぐらへ集合します。場所によっては数千羽以上集まり、鳴き声やフンが問題になってしまうこともあります。博物館付近では国道16号線沿いのケヤキにねぐらができることが多いので、そろそろそんな光景が見られるころかもしれません。
(生物担当学芸員)


























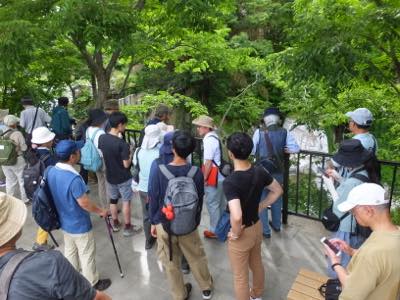

















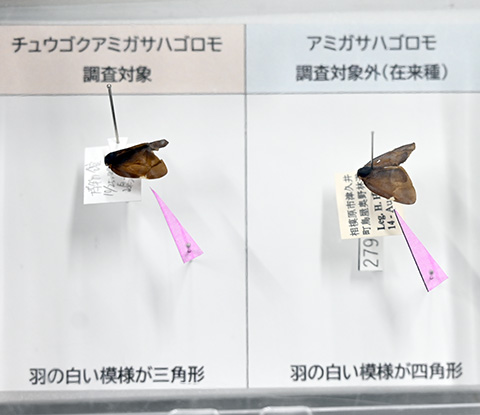


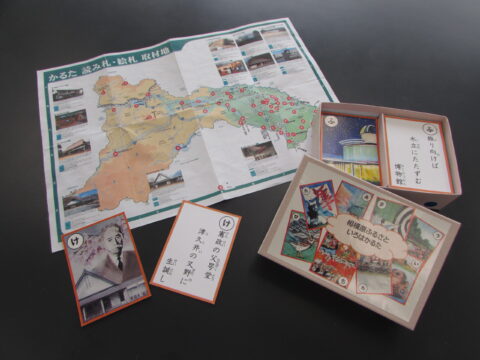

-scaled-e1749963562338.jpg)


