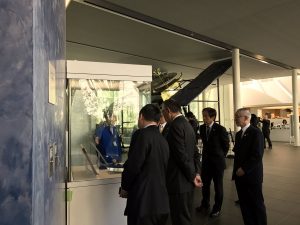★★毛虫と蛾の卵の写真を掲載しています。毛虫が苦手な方、トライポフォビア(いわゆる、ブツブツ恐怖症)の方は見ないでください。
博物館周辺の樹林地で、この4年間ほど続くキアシドクガの大発生も、今年が5年目です。一般論として、キアシドクガの大発生は5年を超えて続くことはまずないとされています。さて、今年は・・・
すでに、2齢以上となっている幼虫が確認されています。ミズキの幹に産み付けられた卵も多くが孵化して空になっています。
当然ながら、すでに若葉が食べられ始めています。例年とくらべて2週間くらいは早い発生と考えられます。
さて、ここからが重要な点です。ミズキの葉の展開がまだ不十分なこのタイミングでこれだけ発生しているとなると、当然のことながら、多くの幼虫が食糧不足に陥り、餓死するでしょう。今年は場合によって連休前半には終齢幼虫が目立つと思われますし、連休の終盤には成虫の発生が見られるかもしれません。しかしおそらく、その数は昨年の爆発的な発生とはほど遠いものになるものと思われます。
「5年程度で終息」とされるキアシドクガの大発生ですが、そのしくみがなんとなく見えてきたように感じられます。引き続き、推移を見守りたいと思います。