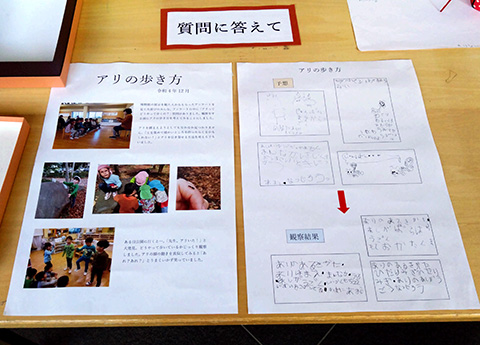12月10日、今月の生きものミニサロンで使用する材料採集の下見に市内の何カ所かのフィールドを巡りました。今月は、毎年恒例になっている。「自然の素材だけでクリスマスリースを作ろう」(12月17日実施)です。リースの台になるクズのつるの状態や、果実の実り具合などを確認するのが目的でした。
さてそんな中、南区下溝でチョウゲンボウの若い個体を見つけました。堤防の法面(のりめん)上空を低く飛んでいます。

低く飛ぶ若いチョウゲンボウ
そのうち地面に下りて、刈り込まれた草地をゴソゴソしています。

地面でなにやらゴソゴソ
そして飛び立ち、近くの杭に止まりました。どうやら、コオロギの仲間を食べているようです。

小さな昆虫を大切そうに食べています
チョウゲンボウはハヤブサの仲間で、小鳥やネズミ、昆虫などを主に食べます。近くにはハクセキレイなど小鳥がたくさんいるのに、どうやらこの若いチョウゲンボウはそうした鳥のハンティングはまだ苦手なようです。昆虫に栄養が無いわけではないのですが、ドタバタと動き回っているわりに獲物は小さく、効率的とは言えません。寒くて動きが鈍くなった昆虫で糊口(ここう)をしのいでいる、というのが実情でしょう。
そして、上空ではこんなバトルが。ハイタカが、ハシブトガラスの攻撃を受けていました。カラスの仲間は、自分たちの存在を脅かす可能性のある猛禽類に対して、徹底的にスクランブルをかけて攻撃します。

ハシブトガラス(上)とハイタカ(下)
大きさが二回りほど大きなハシブトガラスから執拗(しつよう)に攻撃され、ちょっとハイタカがかわいそうになりました。

執拗に攻撃を受けています
肉眼で見えないくらい高い空へ上がったところで、ハシブトガラスはやっと諦めたようです。
勇猛果敢(ゆうもうかかん)なイメージの強い猛禽類ですが、生きていくのは大変だということを実感する光景でした。