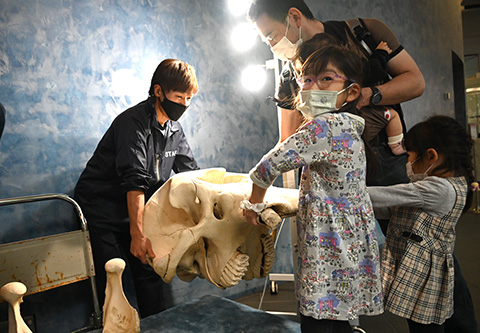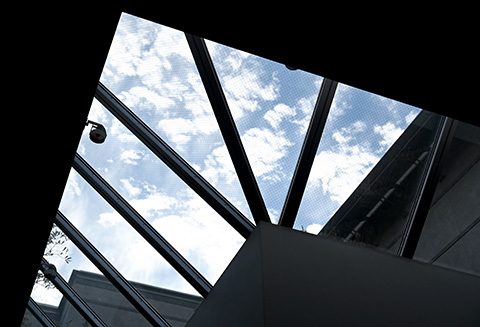先日、市内南区の小学校へ行きました。出張授業の下見です。学校には、植栽されている定番の樹木がいくつかあります。その代表格はサクラ(ソメイヨシノ)ですが、もうひとつ、マテバシイも定番です。

マテバシイ
マテバシイはブナ科の常緑樹で、大きめのドングリがなる木として知られています。

マテバシイのドングリ
もともと相模原には自生していません。日本では紀伊半島や四国、九州、南西諸島のほか、関東地方では、千葉県の房総半島南端部にも自生します。そして、相模原市内では、学校の他に公園でもよく植栽されています。
さて、その小学校にもマテバシイがたくさん植えられていたのですが、落ちているドングリに目が留まったため、拾って博物館へ持ち帰りました。

大きな穴があいたマテバシイのドングリ
落ちていたドングリに、かなりの割合で大きな穴が開いていたのです。ドングリの殻、しかもマテバシイの殻は、例えばコナラやシラカシ、クヌギなどのドングリと比べてとても固いのです。その殻をこのようにかじって開けることができるのは、ネズミの仲間と考えられます。学校周辺に生息するなら、アカネズミでしょうか。

中身が食べられています
ちなみに、マテバシイのすぐ近くに植えられていたコナラのドングリには一つも穴は開いていませんでした。これは何を意味するのでしょうか。コナラのドングリには、タンニンが多く含まれるため、人が食べようとしてもとても渋くてそのまま食べることはできません。野鳥の中にはカケスやオシドリのようにドングリを好んで食べるものもいますし、哺乳類ではツキノワグマが好んで食べることが知られています。しかし、ネズミはタンニンを嫌うため、コナラなどのドングリは食べません。
一方、マテバシイのドングリはタンニンが微量にしか含まれないため、渋くなく、生でも食べられます。これまで、マテバシイのドングリにこのような穴が開いているのを見たことがありませんでした。もともと自生していないマテバシイのドングリを、小学校周辺にすむアカネズミは食べる習性が無かったのでしょう。しかし、アカネズミの中で、チャレンジャーの個体がマテバシイを食べてみて、渋くないことを「発見」し、食べる習性を獲得したと考えられます。他の学校や公園のマテバシイのドングリも、よく観察してみようと思います。