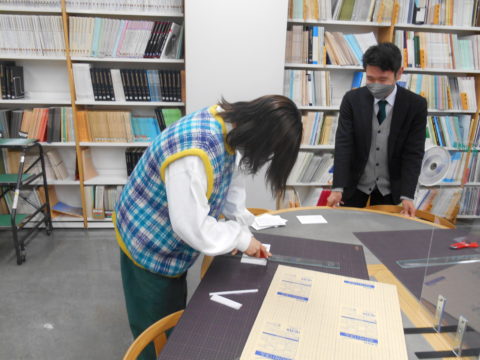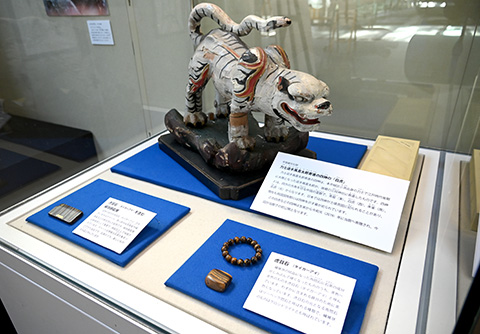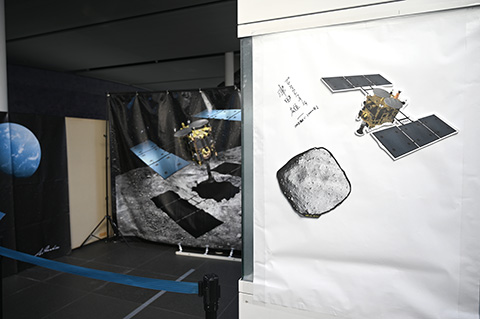12月も中旬になり、日によって寒暖の差はありますがすっかり冬の装いになってきました。これまで撮影してきた写真の中にも、冬を感じさせるものがいくつかあります。
次の写真は漬物用の大根干しで、南区下溝(平成10年[1998]11月20日)です。農家では大根をたくさん干し、それを漬けこんだ自家製のタクワンは食事に欠かせないものでした。二枚目は、切り干し大根用に干しているところで、こうするとさらに保存できました(緑区根小屋・平成22年[2011]1月14日)。 
農家にとって屋敷の庭は、さまざまな作業を行う重要な場でした。それが冬になると寒さで霜(しも)がおりて土が凍り上がるのを防ぐため、ニワブタと言って藁を庭に敷いておきました。本ブログNo.47「藁仕事」でも南区古淵の写真を紹介しましたが、今回挙げたのは、上が南区下溝(昭和62年[1987]12月22日)、下が中央区上溝(平成17年[2005]1月9日)で、こうした日々の備えをしておくのも農家にとって大切なことでした。 なお、一枚目の写真の左側に、やはり大根が干されているのが見えます。 

次の写真は文化財記録映画「相模原の炭焼き」撮影の際のもので、本ブログNo.34「山仕事」でも扱った木を伐採している様子です(昭和61年[1986]12月16日)。木を伐るのは冬場の大事な仕事で、伐った木は自家用というより薪(たきぎ)や炭焼きの材料として販売されました。 
また、建築用の木の製材をする専門の木挽き(コビキ)も各地にいました。写真は中央区淵野辺本町(昭和60年[1985]9月29日)で、丸太を組んで木を固定し、大きなノコギリで板にする作業を再現していただいたものです。当時でも木挽きの経験のあるご存命の方は少なく、貴重な記録と言えます。 
そして、いよいよ年の瀬を迎えると正月の準備に取り掛かります。次回からは改めて正月に関する写真を取り上げたいと思います。