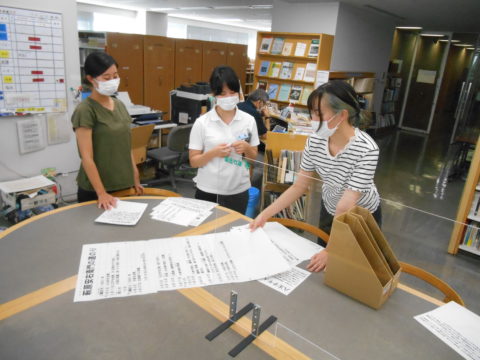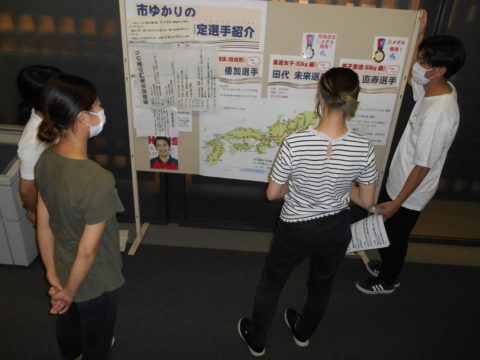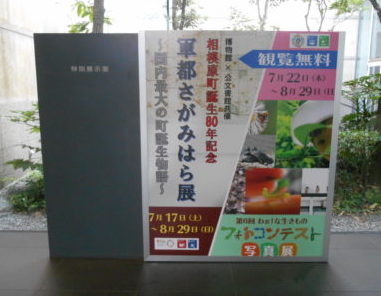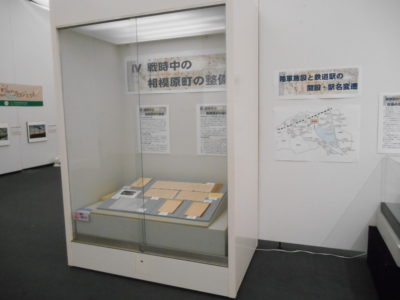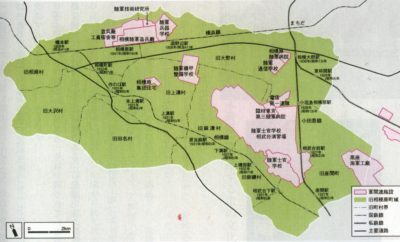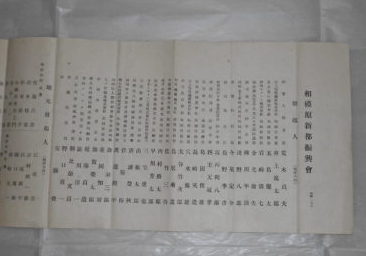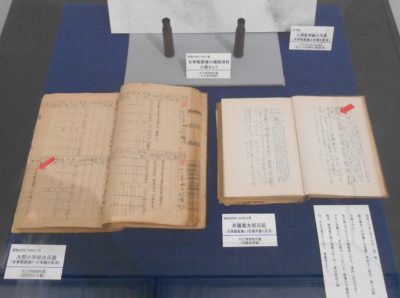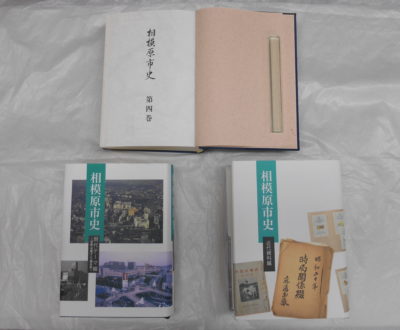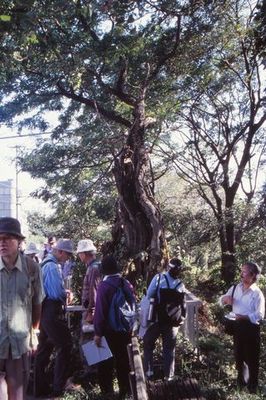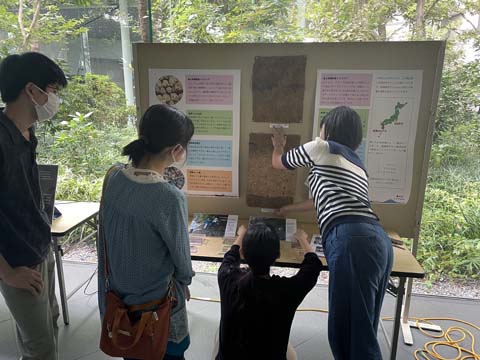博物館では、市内で発見された生きものの問い合わせが頻繁にあります。中でも、特定外来生物に指定され、人間に対して害を及ぼす可能性があるものは、市民から直接持ち込まれるほか、外来生物や衛生害虫などを扱う部署からも持ち込まれることがあります。最近多いのはゴケグモ類とヒアリの疑いのあるものです。先日、「ヒアリではないか」と持ち込まれたものがこちらです。市内ではまだヒアリの確認記録は無いので、ちょっと緊張しながら入れられてきた容器内を見ると・・
体長6ミリメートルほどで光沢があり、赤味がかった小さなアリ(のようなもの)。確かに、環境省が公開しているヒアリ情報の特徴にも一致します。でもでも、上の写真をよく見てください。脚の本数が・・8本あります。昆虫であるアリは、6本のはず。そうです、これは、アリではなく、クモなのです。アリグモ類という、アリそっくりに擬態(ぎたい)したクモの仲間の一種です。
アリグモ類のオスは触肢(しょくし)と呼ばれるクモ類特有の頭部の部位がとても大きく、よく見るとアリっぽくないのですが、これは、アリが物を運んでいるところに擬態しているという説もあります。そもそも、なぜアリに擬態しているのかというと、アリを嫌う(食べない)動物も多く、そうした動物からの捕食を避けるためと言われています。
1枚目の写真のアリグモの仲間(おそらく、ヤガタアリグモ)は、触肢が発達していないのでメスでしょうか。それにしても、アリとよく似ています。クモの眼は8個あるので、多くのクモの顔つきは昆虫とは似ていないのですが、アリグモ類はそのうちの1対を大きく目立たせて、アリに似せています。
ここまで徹底して擬態しているのが災いして、海外から持ち込まれたヒアリとも似てしまいました。捕獲されて毒の生きものの疑いがかけられてしまうとは・・このアリグモもまったくの想定外だったことでしょう。
ちなみに、アリグモ類は、クモ類の中ではハエトリグモの仲間です。あの、家の中をピョンピョンと飛び跳ねて蚊やハエを捕まえてくれるかわいいクモです。
アリグモ類は家の中には入らずに、樹林や草原に住み、植物の葉の上などで小さな昆虫を捕食します。ほかのハエトリグモ類と同様、人間にとってまったく害は無く、蚊やハエを獲ってくれるなど、人には良いことしかしない生きものです。なるべく、ヒアリと間違われないことを願うばかりです。