エナガはいま、子育てのまっさかりです。4月21日、相模川の河川敷の樹林では、巣立ったヒナを連れた家族群が慌ただしく飛び回っていました。ヒナは親鳥ほどではないものの、いっちょまえに尾が長いのですが、顔つきは幼いですね。

エナガの巣立ちビナ
巣立ちビナは、あちこち動き回りながら親鳥から餌をもらうのですが、数十分も動いていると疲れるのか、ヒナ同士集まって休みます。その際、ピタッと体をくっつけ合います。

3羽でくっつきあう巣立ちビナ
野鳥の多くは、ひとたび巣立ってしまうとこうして体をくっつけ合うことはしません。しかしエナガは巣内でぎゅうぎゅうになっていたころの名残なのか、巣立って1週間ほどはこのようにくっつきあいます。この様子は「おしくらまんじゅう」とか「エナガ団子」などと呼ばれ、バードウォッチャーが見たいシーンの一つです。
そして、人間のおしくらまんじゅうは外側から押し合って、内側が押し出されることが多いのですが、エナガの場合は内側に強引に入りたがります。

強引に内側へ入ろうとしています
休んでいるのか遊んでいるのかわかりませんが、こんな押し合いへし合いの最中も目をつむって眠っているヒナもいます。

この時は、5分ほど団子になってからまた散り散りになって飛び回り始めました
この群は数えてみたら、14羽のヒナがいました。そして、餌を与えている成鳥が少なくとも4羽。エナガを含めて多くの野鳥が、繁殖に失敗したつがいや、早く生まれた兄弟が子育てを手伝うことがあり、これをヘルパーと呼んでいます。
この群も、近くで外敵に巣を落とされるなどして繁殖に失敗したつがいが加わっていたものと思われます。
(生物担当学芸員)



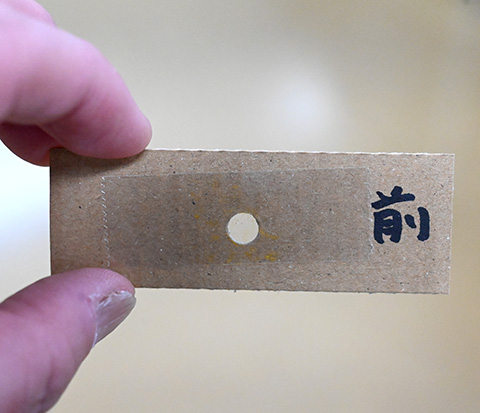
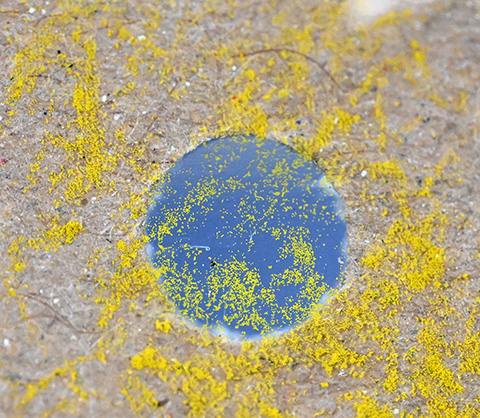


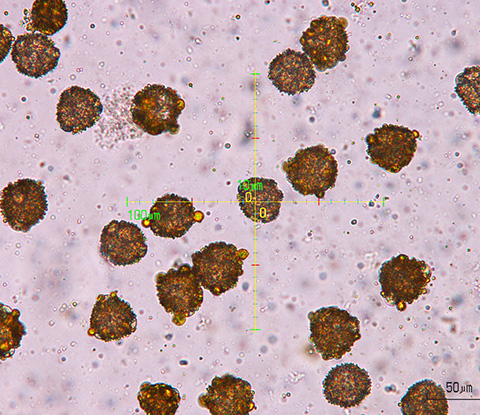
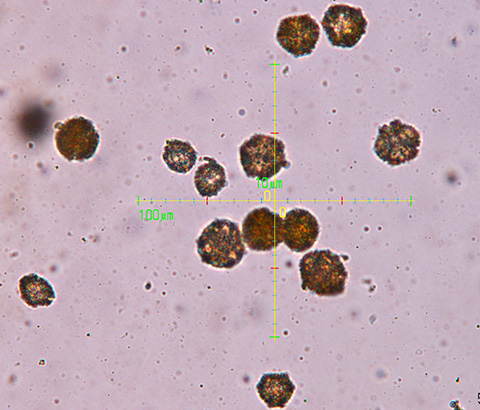

















-1-1-scaled-e1712882114494.jpg)
-2-1-scaled-e1712885483496.jpg)



-scaled-e1712826354749.jpg)





