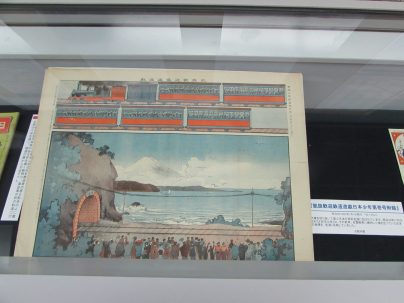前回は、人の一生の中でも婚礼の資料を取り上げました。今回は子どもの誕生や成長にまつわる資料です。
最初の写真は、南区下溝で昭和18年(1943)に生まれた女児のオビアケ(宮参り)の際に、中央区淵野辺の実家から贈られた着物です。前回、昭和17年に結婚した方が使った髪飾りを紹介しましたが、その翌年に誕生した長女のものです。第二次世界大戦中の物資の乏しい時代で買うこともできず、実家で持っていた糸を染めて織ってもらいました。 
糸に挽(ひ)いても良い生糸にならない屑繭(くずまゆ)を、枠(わく)に引っかけて広げて作る真綿(まわた)は、布団の中の綿が寄らないように入れるほか、寒い時期には背中に入れたり、首に巻いたりしました。
そして、子どもが生まれて初めて外出する時や宮参りの時に真綿を子どもの頭に掛けることがあり、髪の毛が真綿のように白くなるまで長生きできるようにという願いが込められています。この真綿は、東京の実家から中央区上溝の孫に贈られたものです。 
次の写真は、最初の宮参りの着物を着た女児の七歳の祝いの着物で、やはり母親の実家から晴れ着が届けられました(収集地・南区下溝)。そして、この際には親戚からも髪飾りや履物などが贈られ、二枚目の写真は親戚から貰ったポックリです。ポックリは、宮参りだけでなく、何かお祝いがある時や正月などにも履きました。 

女児が生まれて初めての三月節供(せっく)に雛人形が贈られます。次の写真は、昭和10年(1935)の南区下溝の旧家のもので、御殿の中に人形が見えています(前の着物をいただいた家とは別)。雛人形にも移り変わりがあり、昭和初期には御殿飾りも出てきて、その後、現在のような段飾りが主流になりました。 
最後の写真は雛人形と同じ家からの寄贈で、男児の五月節供用の内幟(うちのぼり)です。五月節供には、実家から鯉幟(こいのぼり)や幟旗(のぼりばた)が贈られ、こうした家の中に飾るものもありました。

人が生まれてから成長し、やがて老いていくまでの人生の折り目にはさまざまな儀礼が行われ、それは現代でも同じです。今後とも、この地域の人々の人生儀礼のあり方について、資料を基に明らかにしていければと思います。