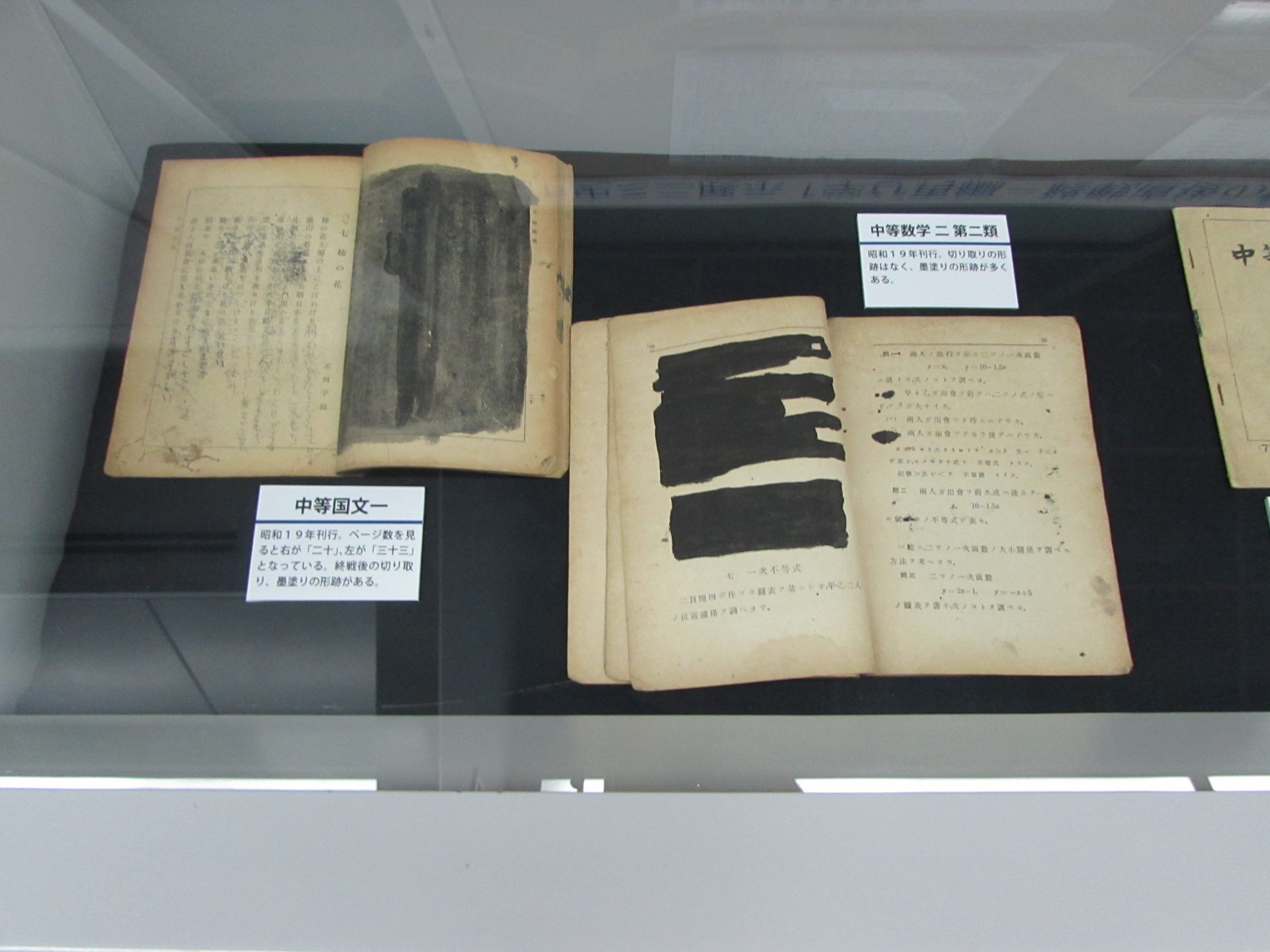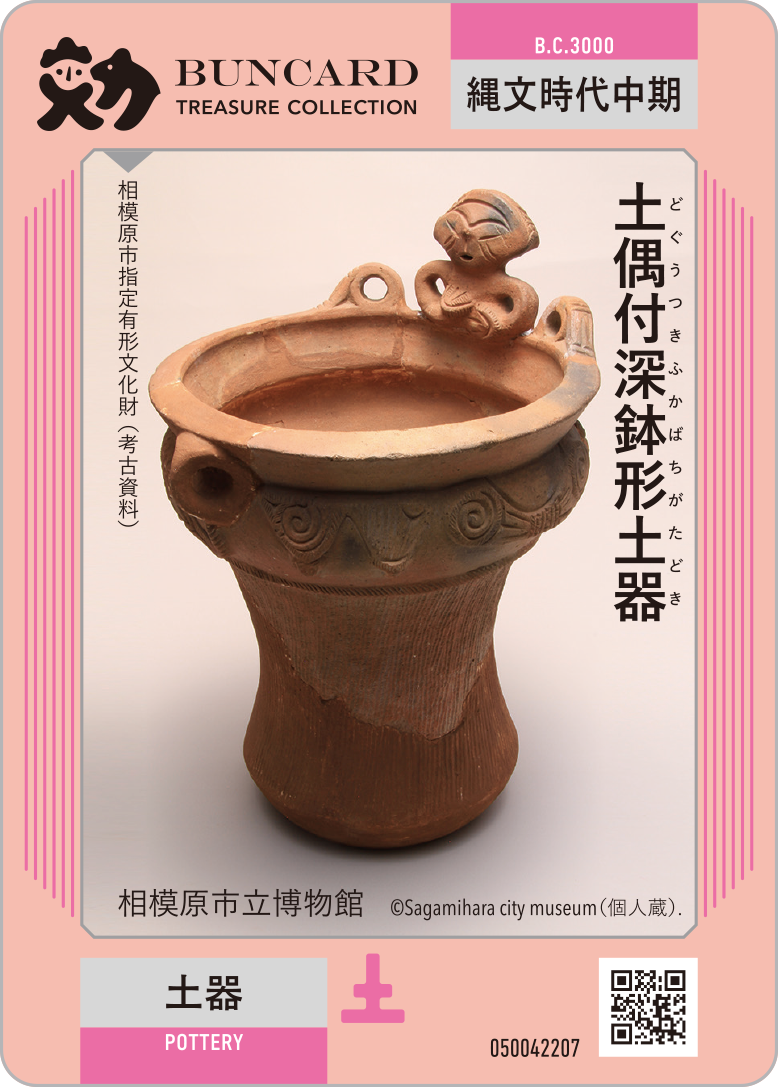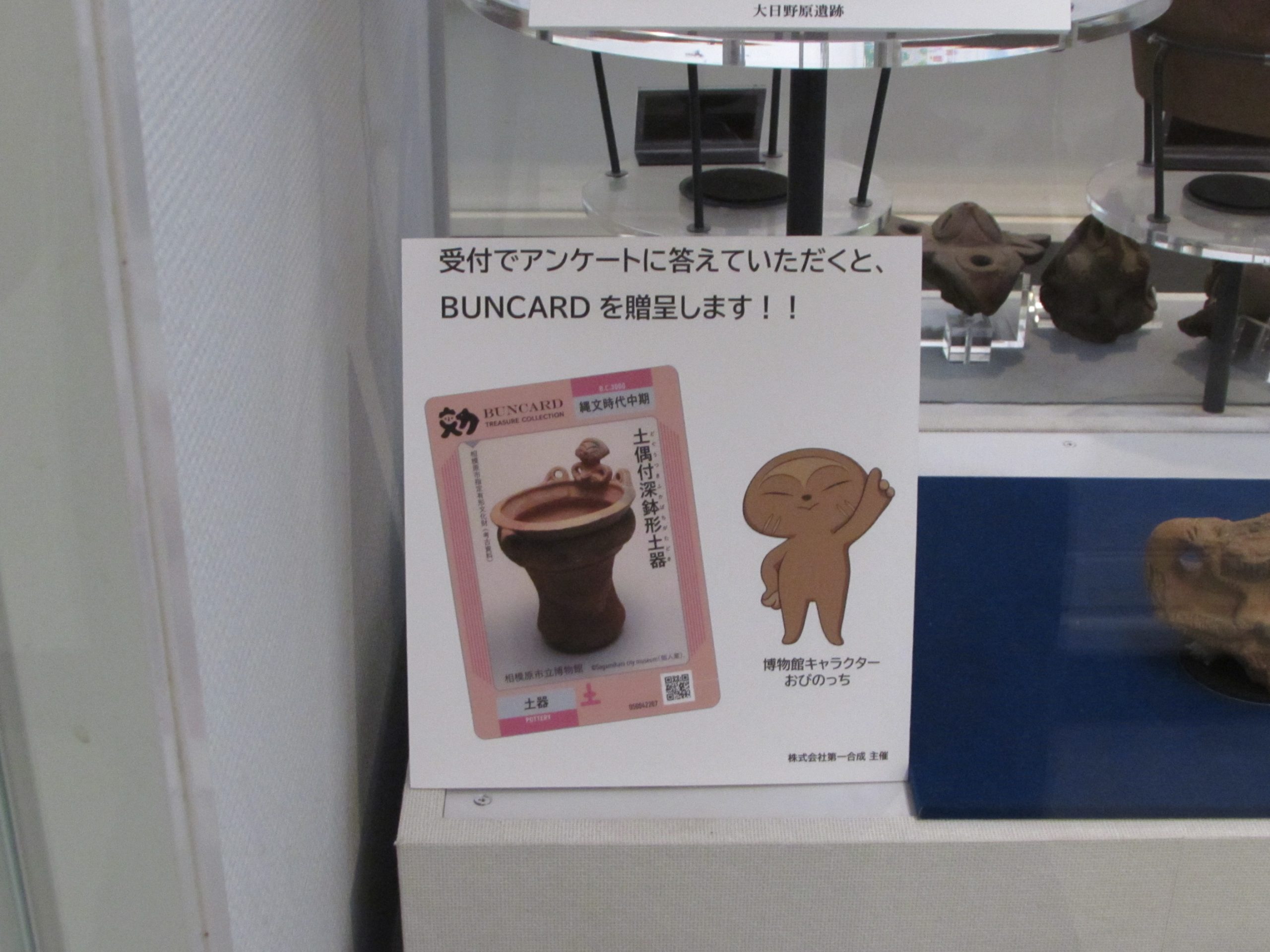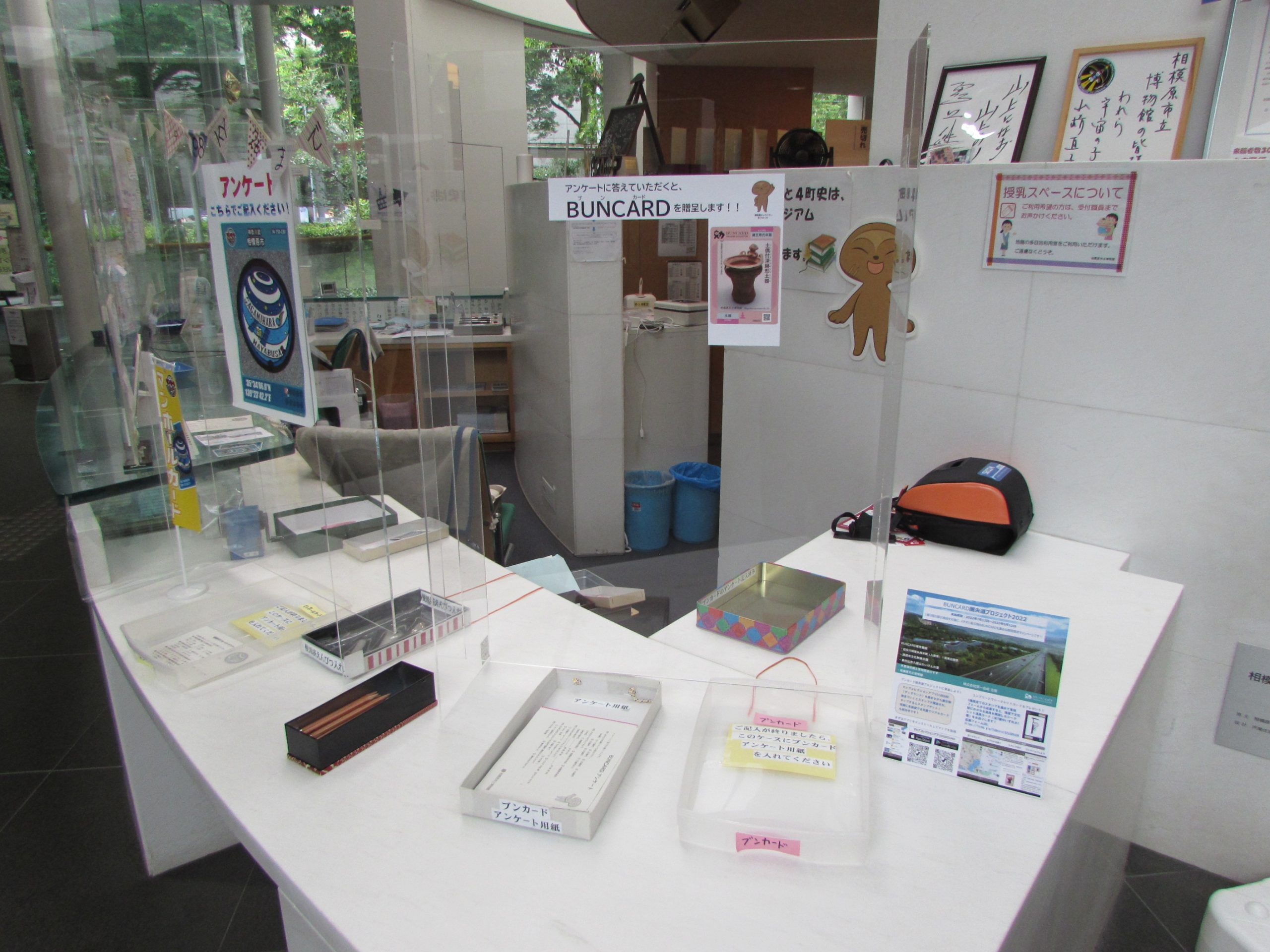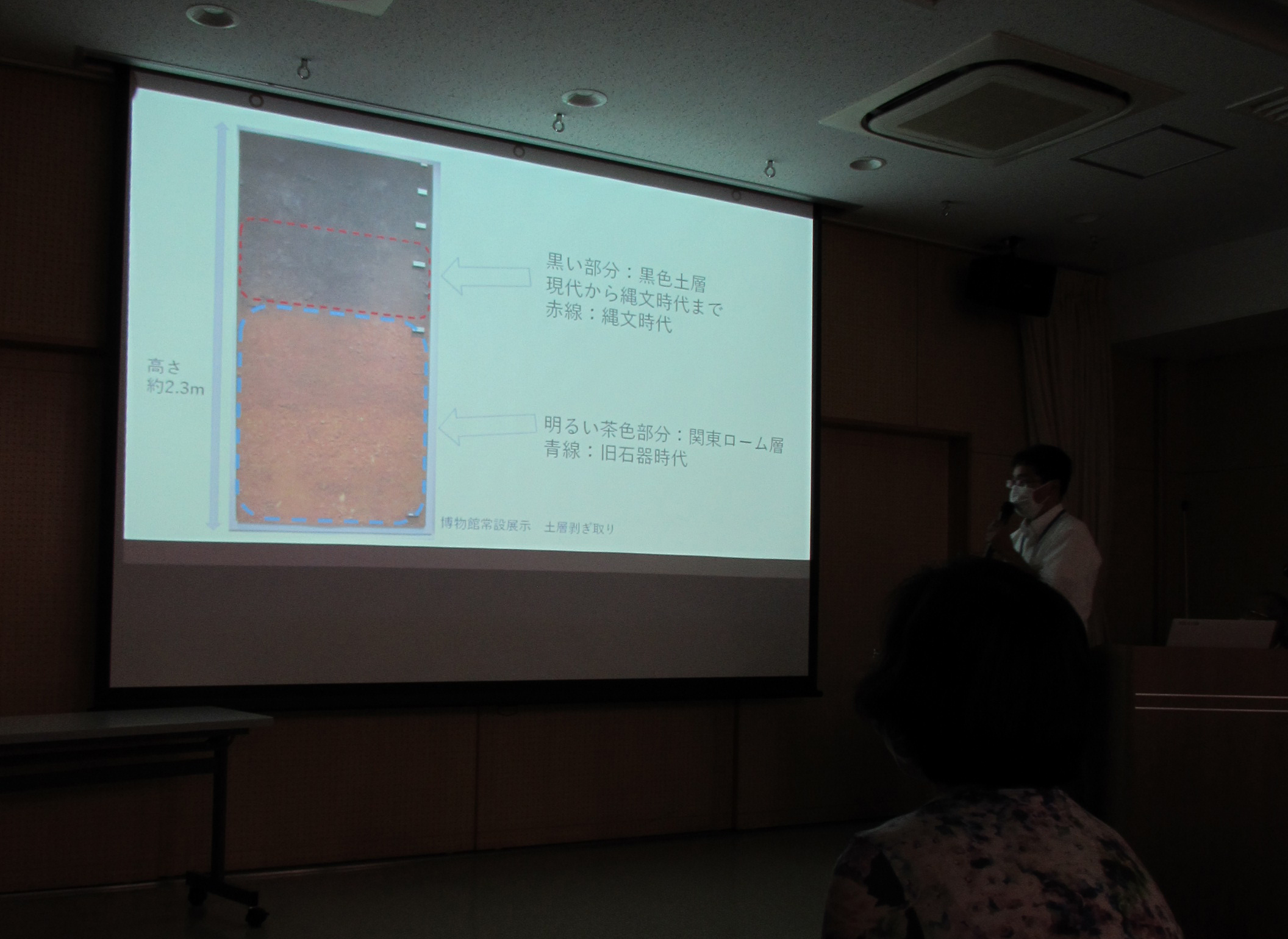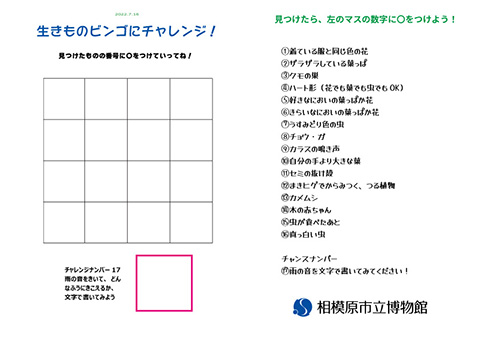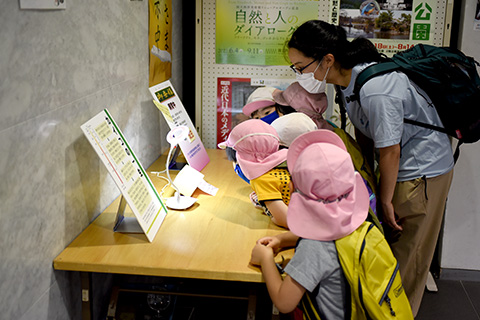私たちの回りにはさまざまな虫が見られますが、その中でも蠅(はえ)は伝染病を運び、また、家畜や農作物に害を与えるものとして嫌がられたものの一つです。
昔は多くの蠅が食べ物や赤ん坊の顔などにたかって、手で払いのけるようだったとの話もよく聞かれるところで、蠅を取る道具も各家にありました。
最初の写真はガラス製の「蠅取り器」です。ちょうどタマネギのような形で、底は中央が内側に丸く湾曲して立ち上がっています。容器の下に食べ物を置いておくと、下側の隙間から蠅が入りますが外に出ることができず、湾曲した部分に入れた水に落ちてしまいます。
南区下溝の方からの寄贈で、第二次世界大戦後に、粘着性のある薬品を塗った蠅取り紙が出まわるまではよく使っていたそうです。 
また、天井に止まっている蠅を捕らえる、ラッパ状の口に細長い管を付けて下の丸い溜まりに水を入れて使う「蠅取り器」もありました(収集地・南区磯部)。


こうした道具のほかに、蠅を叩いて打つ「蠅たたき」もあります。写真は叩く部分が樹脂製で、広く販売されていました。南区の相武台団地にお住まいだった方からの寄贈で、農家だけでなく、コンクリートでできた住宅でも必需品でした。 
最後の写真は「蠅帳(はえちょう・はいちょう)」です。食卓に置かれた食べ物を蠅から防ぎ、また、風通しをよくして食べ物が腐らないように被せるもので、四本の骨があり、傘(かさ)のように開閉することができました。こちらは南区上鶴間団地で昭和33年(1958)に結婚した当時に購入されたとのことで、団地に入居した当時は蠅が多かったそうです。 
現代は衛生状態も改善され、家庭の中で多くの蠅を見ることは少なくなりましたが、今回紹介した道具からは、蠅などの害虫を防ぐための工夫をしてきた生活の様子を知ることができます。