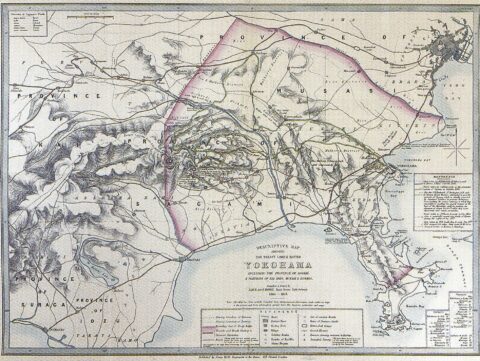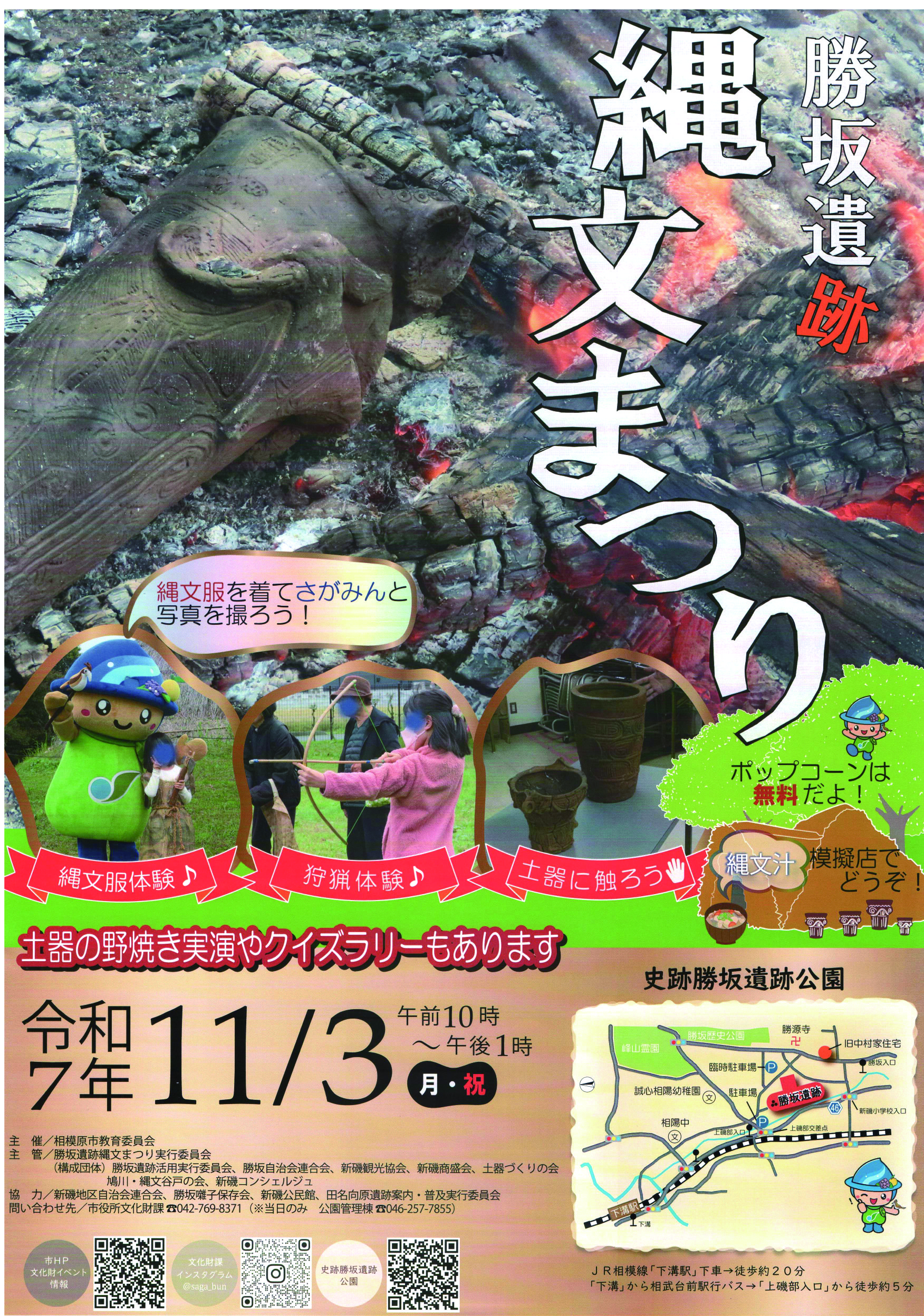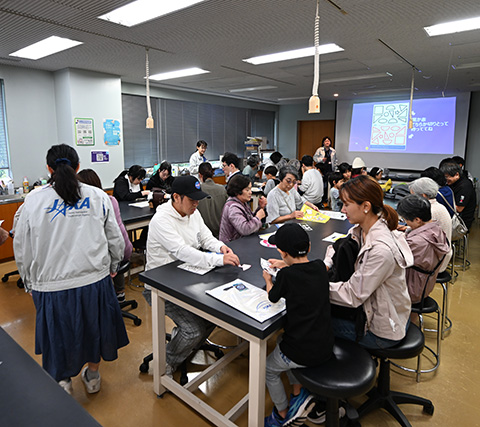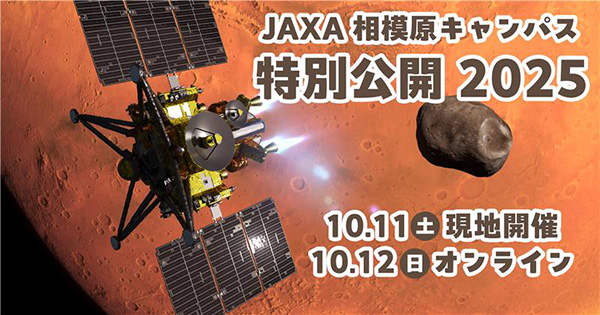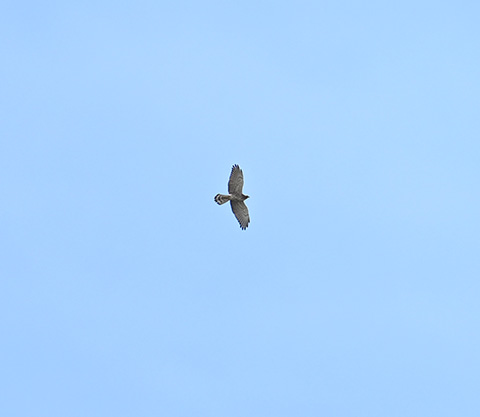8月のこのブログで、クサギの開花について取り上げ、秋に実る果実の写真もアップしました。クサギの果実は、コントラストの強い色の組み合わせにより目立たせていて、これを二色効果と呼ぶことも紹介しました。博物館の周辺でも、その果実が実っています。

クサギの果実
毎年見ていますが、この造形には本当に惚れ惚れしてしまいます。赤く星形に開いているのは萼片で、花の後にいったん閉じて、果実が黒紫色に熟すと再び開きます。二色効果は、赤い萼片とその背景にある緑の葉との補色の関係を指しますが、さらに黒紫色の果実も加わり、三色効果と呼びたいくらいです。

クサギの果実(アップ)
そして、こちらもやはり二色効果の果実、ゴンズイです。

ゴンズイの果実
鞘状の袋果(たいか)が開いて中から黒く熟した果実が登場します。こちらは動物的で、なんともかわいらしい果実です。
どちらも樹林地に普通の樹木ですが、見つけるとついたくさん写真を撮ってしまいます。
(生物担当学芸員)