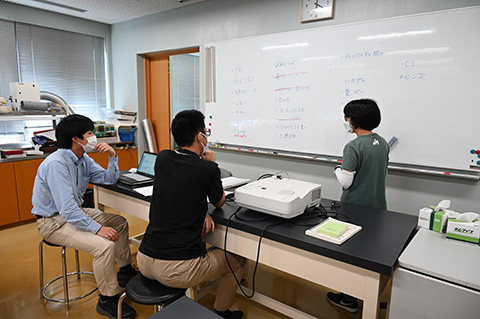前回まで行火(あんか)や火鉢などの、暖房に使う道具を取り上げてきました。こうした道具の熱源としたのは木を焼いて作った炭で、炭はこのほかにも調理をはじめ、蚕を飼う養蚕の際に部屋を暖めるなど、さまざまな用途に使われていました。
次の写真の左側は前回も取り上げた「火のし」(収集地・緑区二本松)で、丸い鉄の部分に炭を入れ、アイロンのように熱で布のしわを伸ばすのに使いました。右側の「こて」(中央区清新)は、炭火の中に先の金属部分を差し入れて熱くするもので、裁縫などの際にやはり布に当ててしわを伸ばしました。 
次の写真は「炭火アイロン」(緑区上九沢)で、電気ではなく焼けている炭を直接中に入れて使いました。明治時代に外国から入って来たものですが、煙突(えんとつ)が付いているのが日本独特の形とされています。 
博物館では燃料として炭も保管しており、写真は中央区宮下本町の方からいただいた炭の一部で、養蚕に使うために炭を俵で買ったのではないかとのことです。なお、炭は使う道具の大きさに合わせて割って使いました。 
次の写真は何だと思いますか。市内では津久井地域をはじめ、相模原地域でも各地で炭焼きが行われており、南区大沼地区では、炭を焼くための土窯(どがま)を作る際に唄った「土窯つき唄」が伝えられています。
写真は左側が「つくぼう」、右側は「きね」(南区東大沼)で、いずれも土窯を作る際に土窯用の粘土(ねんど)を叩くのに使います。二枚目の写真はきねのアップで、右側の先端に叩いた粘土の跡が見えます。 

市教育委員会では昭和61年(1986)度に、大沼地区で実に33年振りに再現された土窯作りと炭焼きの様子を記録した文化財記録映画「相模原の炭焼き」を制作しており、この時に実際に使われた「つくぼう」と「きね」も、窯作りを示す大切な資料としてそのまま収集しました。
最後の写真は、この映画において「きね」を使っているところですが、本職員ブログの「写真で見る相模原~昭和・平成の生活と民俗~」「炭焼き」及び「炭焼きの窯作り」
でも、映画制作時に撮影した写真を紹介していますので、あわせてご覧いただければ幸いです。