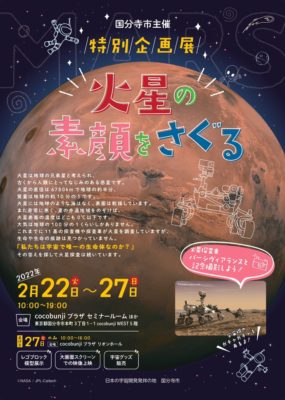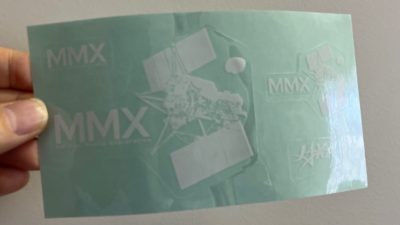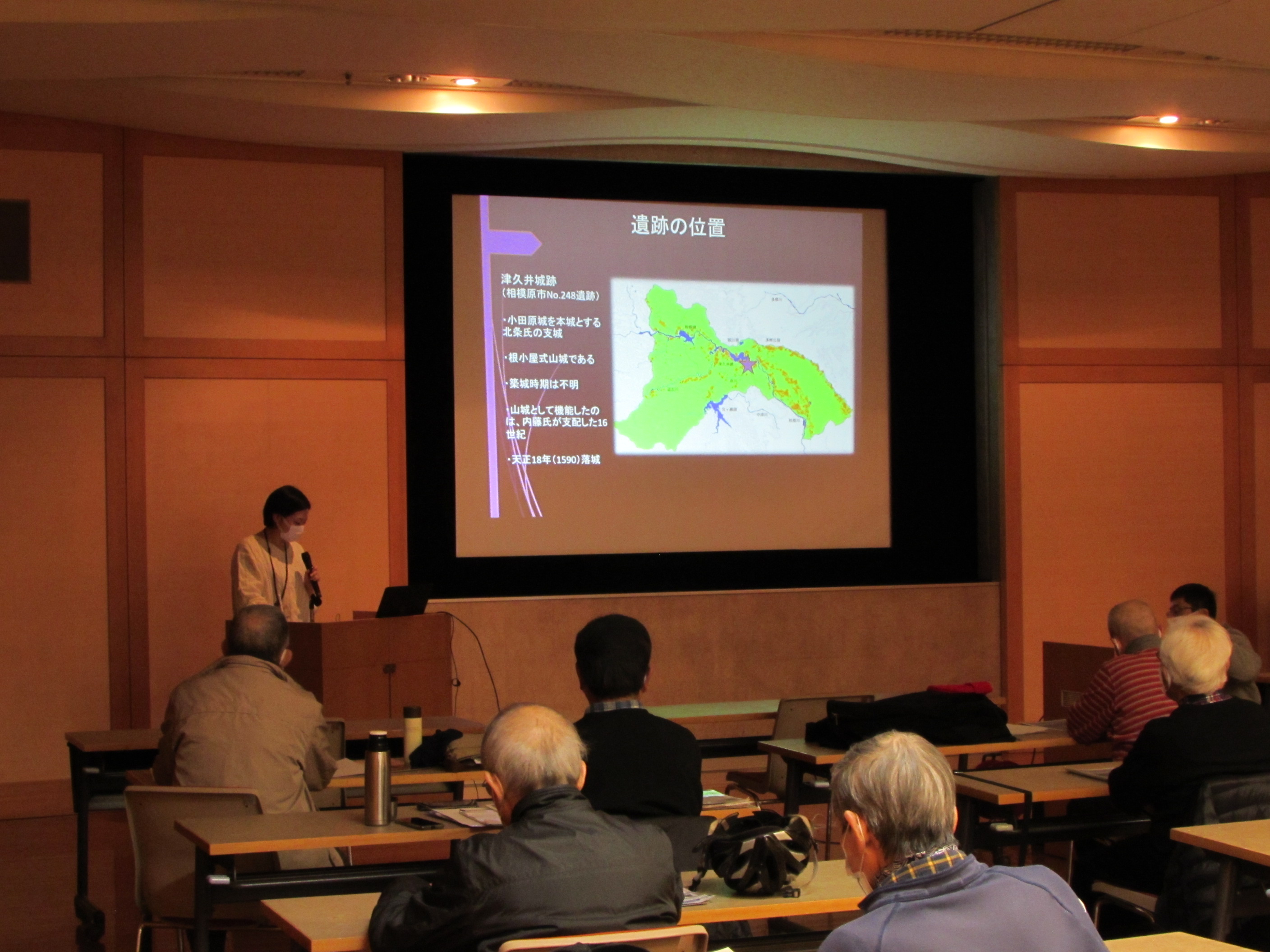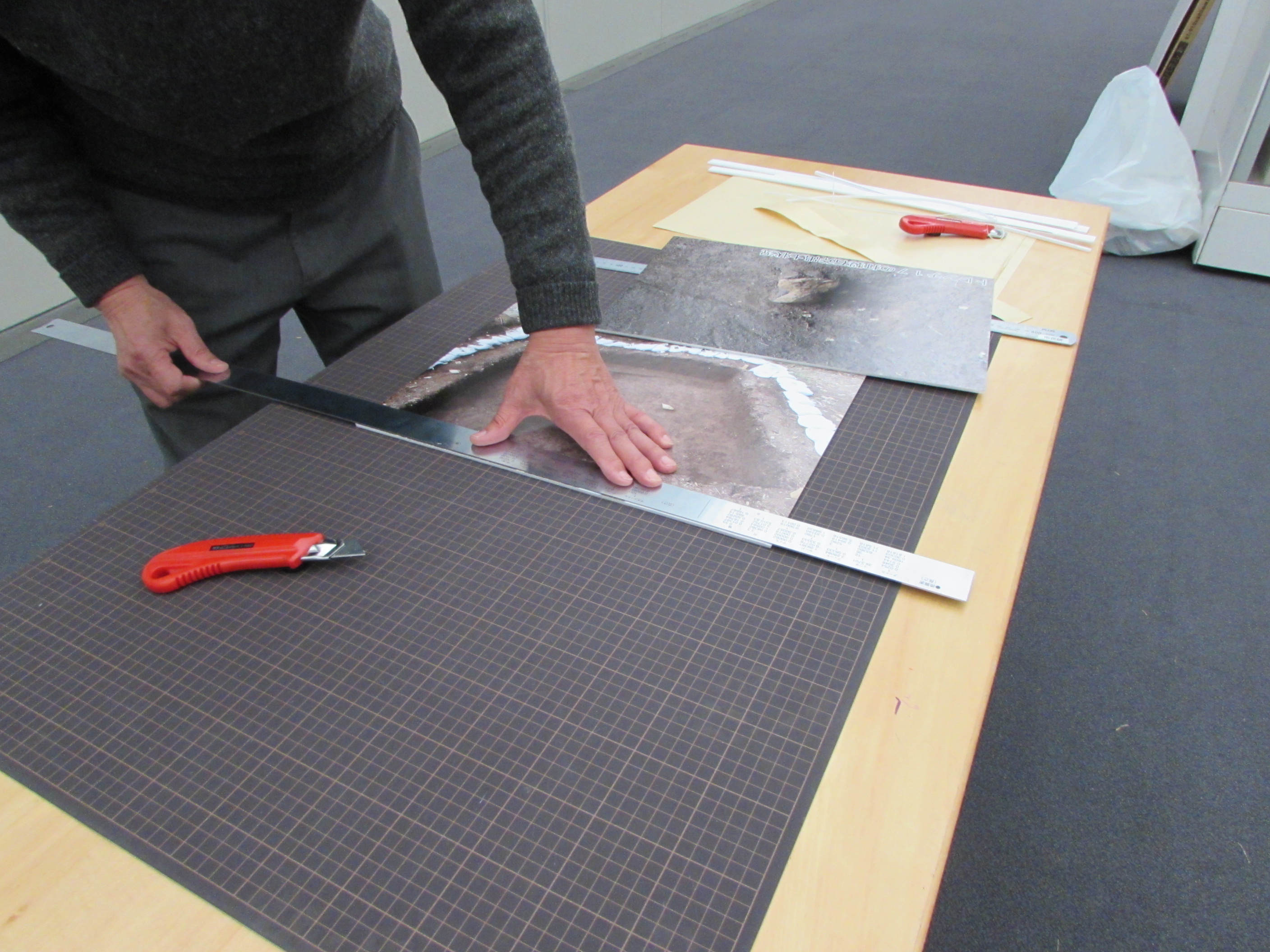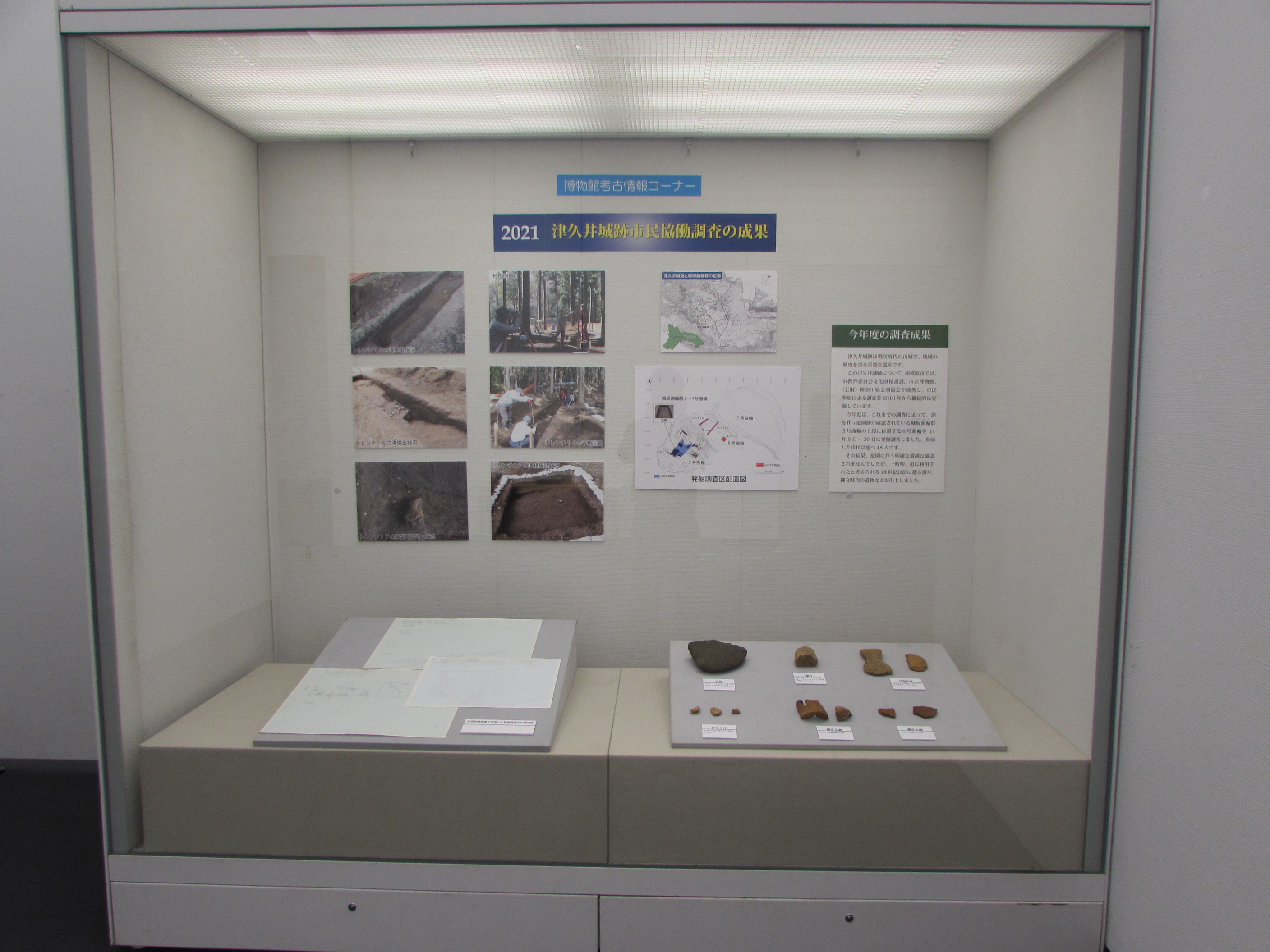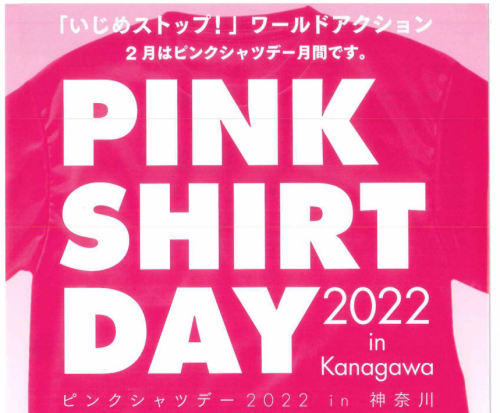土日・祝日などの午前中に投影しているこどもプラネタリウムをご存じでしょうか?
ここ数年は、その季節に見られる星空の話題についての星空生解説と、四季折々のプラネタリウム専用オリジナルアニメ番組の組み合わせでお届けしています。
現在の番組「リーベルタース天文台だより」は、春夏秋冬の季節に合わせ、4つのテーマの番組を上映しています。
今、上映している「リーベルタース天文台だより」冬バージョンの内容は
リーベルタースの森の真ん中には天文台があります。天文台には、いつも子どもたちに星のお話をしてくれる優しい番人、マヌルネコさんが住んでいます。今回、マヌルネコさんは冬の星座の物語「レラプスときつねのおいかけっこ」のお話しをしてくれます。

©TC/ 八木大
という内容で、架空の村の天文台に、動物の子どもたちが集ってきて、星座についてのお話を聞く、というストーリーです。ちょっとレトロな雰囲気のあるアニメを見ているうちに、星座の世界、ギリシャ神話の世界に引き込まれます。
みなさまにお楽しみいただいておりましたが、いよいよ3/5(土)から次のシーズンは、当館オリジナル番組に変わります。そのため、「リーベルタース天文台だより」の上映は、いよいよ2月27日までとなりました。どうぞこの機会をお見逃しなく!(新番組もどうぞお楽しみに)
さて、昨日は2月22日で「猫の日」でした。さがぽんツイッターでもつぶやかれていましたが(そのツイートはこちら)、博物館で猫といえば、「リーベルタース天文台だより」のマヌルネコさんですよね。そしてみなさん、ご存じでしたか?マヌルネコ、というのは物語上の猫の名前ではなく、猫の品種名なのです。検索していただくと、特徴的なずんぐり?まんまる?の猫の画像がヒットすると思います。
そしておまけ情報としては、このマヌルネコさんの骨格標本を見られるところが近くにあるのですが・・・ご存じですか?それは「いのちの博物館」。当館の最寄り駅、JR横浜線淵野辺駅の隣の矢部駅から徒歩5分の所にある博物館です。麻布大学内にある博物館であるといえばピンとくるでしょうか。
動くマヌルネコさんはいませんが、あのマヌルネコさんの骨格はどんな感じなのか?
プラネタリウム番組を楽しんだ後、いのちの博物館にも足を運んでみてはいかがでしょうか。(開館情報などはいのちの博物館のホームページをご覧ください)
プラネタリウムの新番組については、当館ホームページをご覧ください。