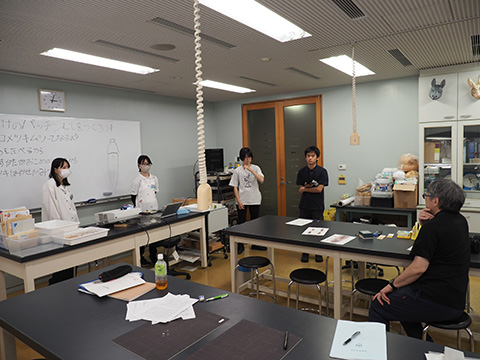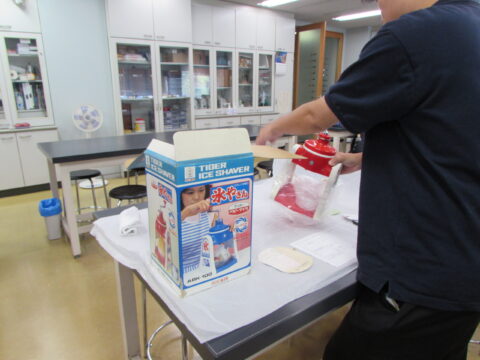ちょっと目を引くタイトルにしようと「肉食?」と書いてしまいましたが、結論から言うと、スズメは「雑食」です。
なぜこんなタイトルにしたかというと、8月26日、市内でこんな写真が撮れたからです。

カメムシをつかまえたスズメ
スズメが植込みにサッと入っていったので、何をしているのかと見ていると、中から飛び出したかと思ったら口に何かをくわえていました。カメムシに見えたので、早速、カメムシ類が専門の当館の動物担当学芸員へ問い合わせたところ、「ホオヅキカメムシではないか」とのことでした。
スズメは手慣れた様子でくわえなおして、そのまま飲みこんでいました。

あっさりと飲み込んでいました
躊躇なく植込みへ入っていったところを見ると、普段からこうしてここで昆虫などを捕食しているのでしょう。
スズメは収穫前のイネを食べる、というイメージが昔から強く持たれています。たしかに、秋の一時期には水田地帯へ大群で押し寄せてイネを食害しますし、秋から冬は地面に落ちた雑草の種子などを中心に食べています。しかし、春から夏はむしろ、こうしてイモムシや蛾の仲間、小さなコウチュウ類など昆虫類、クモ類などをよく食べています。
スズメはイネが主食なのではなく、「雑食」なのです!
(生物担当学芸員)